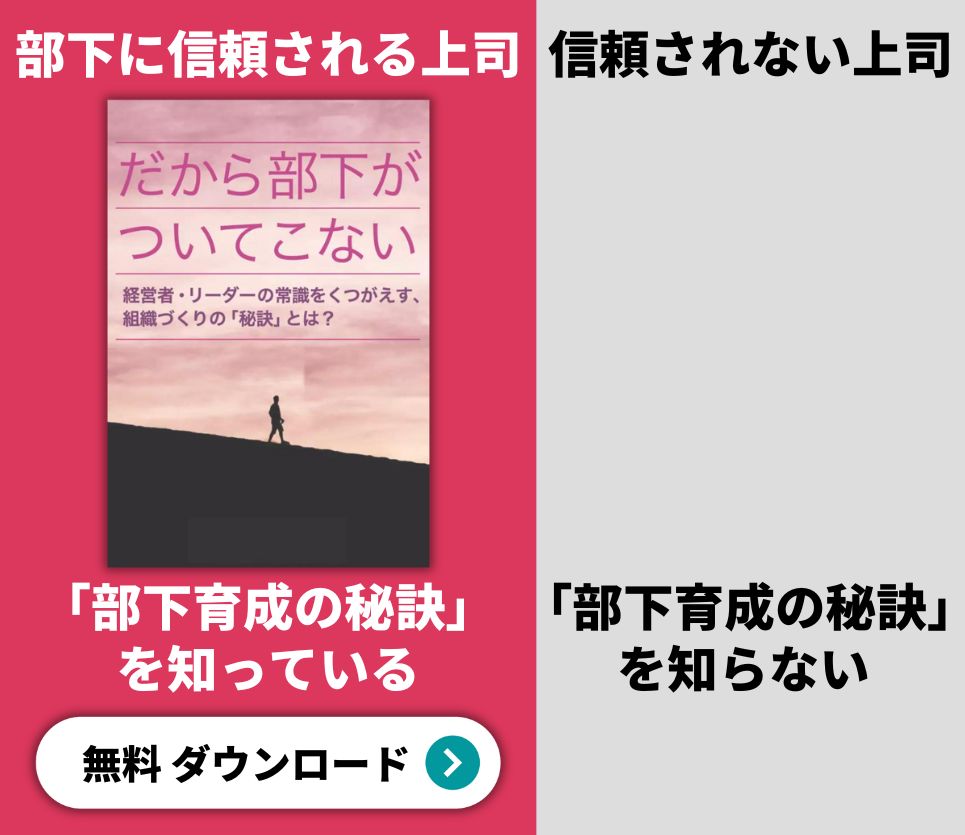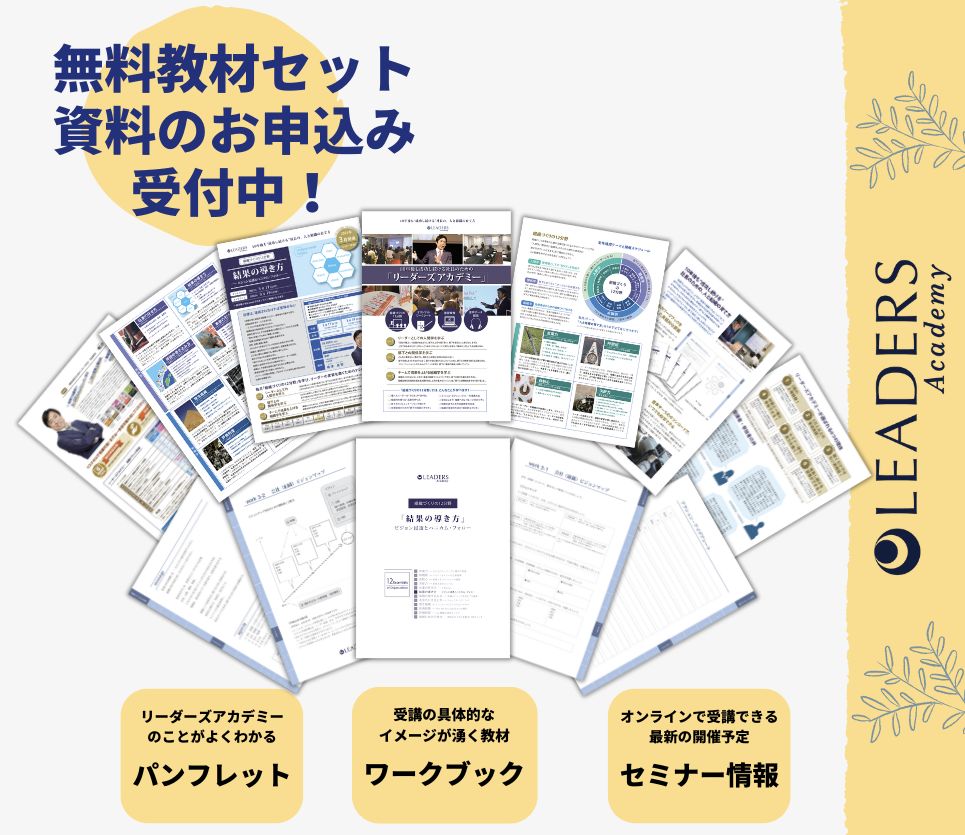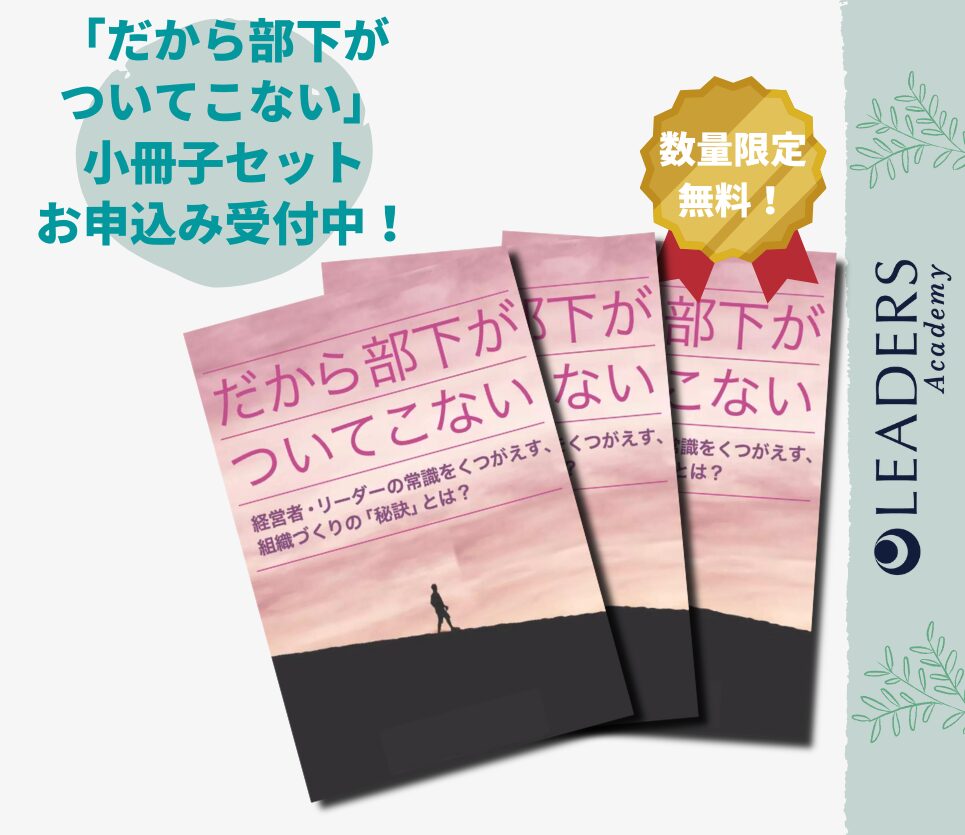経営者にとって、リーダーシップやマネジメントスキルは欠かせないものです。そのため、次のような悩みを抱える方も多いのではないでしょうか。
- リーダーシップとマネジメントの違いや重要性を知りたい
- リーダーシップとマネジメントのスキルの両方を身につけたい
- リーダーシップとマネジメントのスキルを高めた事例を知りたい
本記事では、上記のような悩みを解決するため、リーダーシップとマネジメントの違いについて徹底解説します。
リーダシップとマネジメントの両方を身につける方法や、具体的な事例についてもお伝えしますので、ぜひ最後までチェックしてみてください。
組織づくりに対して悩みがある方は、こちらの記事も参考になります。
» 組織づくりとは?企業を成長させる「強い組織」の作り方 | リーダーズアカデミー
リーダーシップとマネジメントの違いとは

リーダーシップとマネジメントは似たようなスキルに思えますが、実際は以下のような点で異なるものです。
| リーダーシップ | マネジメント | |
|---|---|---|
| 求められるタイミング | ・新規事業を始める時 ・事業の停滞時 ・目標が定まっていない時 | ・目標が明確な時 ・目標達成に向けて具体的なアクションを起こす時 |
| 組織を導く際の視点 | ・中長期的な視点 | ・短期的、長期的な視点の両方 |
| 影響力の要因 | ・リーダーの人格 ・リーダーの考え方 ・リーダーの価値観 | ・肩書き ・地位 ・職務の権限 |
経営学の父と呼ばれるピーター・ドラッガーも両者の違いについて次のように述べています。
マネジメントはものごとを正しく行うこと(doing things right)
リーダーシップは正しいことを行うこと(doing the right things)
このようにリーダーシップとマネジメントは異なるものであることを覚えておきましょう。以下で、具体的な違いについてもお伝えします。
求められるタイミングの違い
リーダーシップは、組織が新たな挑戦をしたり、方向性を大きく転換したりする必要がある場面で求められます。例えば、新規プロジェクトの立ち上げや事業の再構築、危機管理の局面など、従来の枠組みでは対応が難しい状況などです。メンバーが不安や混乱に陥らないよう、未来へのビジョンや大局的な方向性を示す役割を担います。
対してマネジメントは、既に設定された目標に向かって具体的なアクションを起こす時に求められるものです。明確な戦略がある場合、効率的な業務遂行やリソースの最適な配分、進捗状況のモニタリングを通じ、組織全体のパフォーマンスを維持・向上させるためにマネジメントを発揮します。
組織を導く際の視点の違い
リーダーシップは、将来や市場の変化に対応するため、中長期的な視点を持つ必要があります。遠い未来に向けた大局的なビジョンや理念を打ち出し、組織全体にその方向性を浸透させるのが役割です。
一方で、マネジメントは戦略を実現するため、短期的な視点と長期的な視点の両方をバランスよく持つ必要があります。日々の業務効率化やプロセスの最適化、組織内のコミュニケーションの促進など、具体的な施策に落とし込みながら、全体としての戦略達成をサポートするのが役割です。
影響力の要因の違い
リーダーシップにおいては、個人の人格や信念、コミュニケーション能力が大きな影響を持ちます。リーダーは自らの姿勢や行動を通じてメンバーに刺激を与え、共感や信頼を築くことで、自然発生的なフォロワーシップを形成します。肩書きや地位には依存せず、その人自身のカリスマ性や価値観が、組織の雰囲気や文化に大きな影響を与えるでしょう。
マネジメントの場合は、職務上の権限や役割、組織内での地位がその影響力の根拠となります。具体的な業務の遂行やリソースの管理、組織運営のルールに基づいて、計画通りに物事を進めるための実務的な力が求められるのです。
リーダーシップに求められるスキル

リーダーシップを発揮するためには、単に目標を掲げるだけではなく、その目標に向けて組織全体を導き、変化を受け入れながら前進するための多角的なスキルが必要です。具体的には、次のようなスキルが求められます。
- ビジョンを提示して共有する力
- 社内のモチベーションを向上させる影響力
- 変革を推進して時代に乗る力
ここでは、リーダーシップに求められる上記のスキルについて詳細をお伝えします。
ビジョンを提示して共有する力
リーダーは組織の未来像を明確に描き、そのビジョンを具体的な目標や戦略に落とし込む役割があります。またそのビジョンをチーム全体に共有し、組織に対して「何を目指すべきか」を理解してもらう必要があるでしょう。
さらに、リーダー自身がビジョンに対する情熱や信念を持ち、日常のコミュニケーションや行動で示すことも重要です。
組織全体が一体感を持って前進できる環境が整うことで、目標を達成しやすくなります。
社内のモチベーションを向上させる影響力
優れたリーダーは、メンバー一人ひとりの潜在能力を引き出し、チーム全体の士気を高めるための影響力を持っています。適切なフィードバックや賞賛、時には厳しい指導を通じて、個人の成長を促しながら、共通の目標に向かって一致団結させる力が必要です。
信頼関係を築くことで、メンバーは自発的に意欲を発揮し、困難な局面においても積極的な挑戦を続けることが可能になります。リーダーとしての影響力は、組織全体の生産性向上や、チーム内のコミュニケーションの円滑化にも関わるため重要です。
組織が持続的に成長できるよう、モチベーションを向上させるような影響力が求められます。
変革を推進して時代に乗る力
リーダーには、現状に甘んじず常に新たな挑戦をする、変革を推進して時代の波に乗るような力が求められます。市場や技術の進化に敏感に反応し、イノベーションを促進するために自ら戦略を提案・実行していく必要があるでしょう。
また、組織に変革をもたらす時には、社員の抵抗感を和らげ、共に未来の可能性を描く姿勢も重要です。リーダーが率先して変化を受け入れ、柔軟な思考で新たな道に進むことで、組織も時代の流れに乗りやすくなります。
組織が時代の流れに合わせて柔軟に変化できると、持続的な競争力の獲得が可能になるでしょう。
リーダーとしての役割やスキルについてさらに詳しく知りたい方は、下記の記事も参考にしてみてください。
» 期待待外れはリーダーの責任?!仕事を任せた後に、上司がやるべき3つのフォロー
» 信頼関係を築けるリーダーの共通点とは?顧客とどう信頼関係を構築する?
マネジメントに求められるスキル

マネジメントにおいては、組織の戦略的な目標を達成するために、次のようなスキルが求められます。
- 計画・目標設定の能力
- 組織運営・リソース管理の能力
- 問題解決・リスク管理能力
それぞれのスキルについて、詳細をお伝えします。
計画・目標設定の能力
計画・目標設定の能力は、マネジメントの根幹をなす要素であり、組織の未来像を具体的な数値や期限、ステップに落とし込むために必要です。
市場動向や内部リソースを正確に分析し、現実的かつ挑戦的な目標を設定することで、組織が各自の役割を自覚しながら行動しやすくなるでしょう。
また、状況に応じた柔軟な計画の見直しも重要であり、計画倒れしないように組織を導く役割をこなす必要があります。
組織運営・リソース管理の能力
組織運営・リソース管理の能力は、限られたヒト・モノ・カネを最適に活用し、業務全体の効率を高めるために不可欠です。
各部署間の連携を円滑にするだけでなく、業務プロセスや情報の流れを的確にコントロールし、リソースの無駄を最小限に抑えながら最大の成果を引き出すことが求められます。
さらに、リソースの配置や予算配分においては、将来的な成長や突発的なニーズを見越した柔軟性も大切です。適切なリソース管理は、組織が安定して目標に向かって前進するための強固な基盤となり、持続可能な運営体制を築きやすくなるでしょう。
問題解決・リスク管理能力
問題解決・リスク管理能力は、業務の進行上避けられないトラブルや予測不能なリスクに迅速かつ適切に対処するための重要なスキルです。
問題やトラブルが発生した時には、現場からの情報をもとに問題の本質を見極め、原因分析を徹底しながら効果的な対策を講じる必要があります。
さらに、リスクの早期発見とその影響の最小化を図るために、事前のリスク評価やシナリオプランニングを行い、緊急時の対応策を整備するのもマネジメントです。
組織を不測の事態に対して整えておくことで、安定してプロジェクトを進めやすくなります。
リーダーシップなきマネジメントに未来はない

リーダーシップとマネジメントには、相互関係があります。マネジメントだけで会社が成長し続けることはなく、リーダーシップだけで会社を安定させることも困難です。
それぞれ組織を運営すること自体は可能でも、長期的な成長や革新を実現するためには、リーダーシップとマネジメントの両方が不可欠です。
日々の業務管理や効率的な運営は企業基盤を支え、変化の激しい現代においては、未来を見据えたビジョンや情熱、挑戦する姿勢などが求められるでしょう。
強烈なマネジメントだけではなく、リーダーシップとの融合こそが組織の持続的な発展のために欠かせない要素です。
リーダーシップに偏ると実行力が不足する
リーダーが未来へのビジョンや理念に熱心であっても、実際の業務を推進するための具体的な計画や管理が不足すると、組織は目標達成に向けた行動が滞り、現場で混乱を招きます。
業務の進捗管理やタスクの明確な分担がなければ、実行段階での抜け漏れや遅延が発生しやすいのです。
具体的なアクションとしては、明確なスケジュール設定、定期的な進捗確認、適切なフィードバック体制を整備するなどが挙げられます。フローをある程度仕組み化しておかなければ、リソースが偏ったり、主体性のある人だけに属人化してしまったりする恐れもあります。
もしこれらの管理が不十分だと、従業員のモチベーションは低下し、現実と理想のギャップが拡大しやすくなるでしょう。組織の硬直化を招く原因にもなってしまうため、注意が必要です。
リーダーシップにより未来を描く力と、実行力を支えるマネジメントのバランスが取れて初めて、組織は持続可能な成長と成果を生み出せます。
マネジメントに偏ると組織を先導できない
管理や業務の効率化に注力しすぎると、組織は現状維持の状態が続き、変革や革新が停滞するリスクが高まります。数字やプロセスに偏重したマネジメントは、ルーチン業務の遂行には優れていても、未来への挑戦や新たな可能性を追求するためには役立ちません。
むしろ柔軟性や創造性を損なう恐れがあり、結果として、従業員が自発的に新しいアイディアを提案するような環境も失われます。このように従業員の主体性が失われた状態では、市場の変化に迅速に対応する力が弱まってしまい、競争力も低下するでしょう。
モチベーションやエンゲージメントが低下することで、優秀な従業員の離職を招くこともあります。
組織が成長を続けるためには、マネジメントによる現状の管理だけでなく、未来を見据えたリーダーシップによる明確な方向性の提示が必要です。
リーダーシップとマネジメント 両方のスキルを高める6つの方法

「リーダシップとマネジメントの両方が重要である」ということは、お分かりいただけたと思います。しかし、実際にリーダーシップとマネジメントを両立して伸ばし、発揮していくためにはどのようなステップを踏めば良いのか分からない方も多いでしょう。
そこで実践してほしいのが、次の6つです。
- 組織からのフィードバックを取り入れる
- ビジョンとタスクのバランスを意識する
- 問題解決型のリーダーシップを実践する
- ロールモデルを見つける
- 自己評価と目標設定を繰り返す
- セミナーや研修に参加する
1つずつ具体的に詳細をお伝えしますので、実践できそうなものから始めてみてください。
組織からのフィードバックを取り入れる
部下や同僚からの意見や評価は、リーダーシップとマネジメントの両方を向上させるための貴重な資源です。定期的な1on1ミーティングや360度フィードバック、アンケート調査など、さまざまな方法を用いると、現場の声を広く取り入れることが可能になります。
具体的には、オープンなコミュニケーションを心掛けることで、組織全体に透明性と信頼感が生まれ、結果的にリーダーシップを高めやすくなるでしょう。
また、フィードバックを「実践可能なアクション」として組織に落とし込むことで、マネジメントも強化できます。
このように、リーダーとしても信頼を得ながら、現場をコントロールしやすくなり、両スキルの向上が見込めます。
ビジョンとタスクのバランスを意識する
長期的なビジョンと日々のタスクのバランスをとることは、組織全体を効果的に牽引するために非常に重要です。将来的な目標や理想像を明確に描くことにより、全員が共有すべき方向性が定まります。
しかし、いかに大きなビジョンを掲げても、具体的な日常業務が伴わなければ実現は難しいのが現実です。そのため、ビジョンを実現するための中期・短期の計画を策定し、具体的なタスクに落とし込む必要があります。
タスクの進捗を定期的に確認し、必要に応じて計画を見直すことで、理想と現実のギャップを縮小しやすくなるでしょう。
また、目標達成に向けた段階的な評価を行うことも効果的です。ビジョンとタスクの両面を意識することで、戦略的な視点(リーダーシップ)と実行力(マネジメント)がバランスよく発揮されます。
問題解決型のリーダーシップを実践する
問題解決型のリーダーシップは、単にリーダーシップスキルを伸ばすだけでなく、マネジメントスキルの向上にも繋がります。
なぜなら、問題を解決するためには、組織にビジョンを示しつつ、リソースを適切に管理し、現場を動かすスキルが求められるからです。
例えば、他のリーダーシップ型と比較すると、そのバランスの良さが際立ちます。
【カリスマ型リーダーシップの場合】
リーダーの個人的な影響力に依存しやすく、組織全体の自走力や長期的な仕組みづくりが弱くなる傾向があります。
【サーバント型リーダーシップの場合】
組織の意見を尊重しすぎることで、意思決定が遅れ、スピード感を持ったマネジメントが難しくなることがあります。
一方で、問題解決型のリーダーシップは、リーダーシップ(組織を導く力)とマネジメント(業務を最適化する力)をバランスよく発揮できる点が強みです。
例としては、経営哲学としても有名なトヨタの「カイゼン」が挙げられます。「カイゼン」では、実際にビジョンを示しながら、現場の課題解決を日常的に行うことで、組織全体の生産性を向上させています。
このようにリーダーシップとマネジメントの両面を考慮すると、問題解決型のリーダーシップがバランスに優れていると言えるでしょう。
ロールモデルを見つける
経営においてロールモデルを見つけるべきことは周知の事実ですが、実際にどのようなロールモデルを探すのかが重要です。
リーダーシップとマネジメントスキルの両方を伸ばすためには、実際に両スキルを発揮している経営者を見つけるのがベストでしょう。
例えば、先述した「ピーター・ドラッカー」はもちろん、Amazon創業者の「ジェフ・ベゾス」もリーダーシップとマネジメントスキルの両方に優れています。「ジェフ・ベゾス」は明確なビジョンを示しながらリーダーとしての信頼を得つつ、「ツーピザ・チーム」 ルールなどを用いながらチームビルディングや人材育成にも熱心に取り組みました。
「イーロン・マスク」も優れたロールモデルで、大胆なビジョンを掲げるリーダーでありながら、現場にも入り込み、自らエンジニアやデザイナーと直接やりとりすることでマネジメントを徹底しました。また、人材を徹底的に厳選する採用方式を用いたり、最高のパフォーマンスを引き出すために100%ではなく85%の力で仕事をする「85%ルール」を組織に浸透させたりするなど、人材や現場へのこだわりが見られます。
このように、リーダーとしてビジョンを掲げながらも、人材や現場などをしっかりとマネジメントしているロールモデルを見つけることで、両スキルを伸ばしやすくなるでしょう。
自己評価と目標設定を繰り返す
定期的な自己評価と目標設定は、リーダーシップとマネジメントの両方を伸ばすために不可欠なプロセスです。
例えば、自己評価においては、次のような観点で評価を行うことにより、リーダーシップとマネジメントの両スキルを向上させられます。
| 評価項目 | リーダーシップにおける評価 | マネジメントにおける評価 |
|---|---|---|
| ビジョンの明確さ | 長期的な方向性を定めて、チームに共有できているか | ビジョンを実行可能な戦略に落とし込めているか |
| 意思決定の精度 | 直感だけでなく合理性があるか | 現場の負担や課題を考慮した意思決定か |
| コミュニケーション | リーダーとしての尊厳を保ちながら、信頼を得られているか | 明確な指示や情報共有により、組織全体が同じ方向を向けているか |
上記はあくまで一例ですが、リーダーシップにおける評価、マネジメントにおける評価の両方を意識することが大切です。
また、これらの自己評価をもとにして、どのように目標設定するかも重要なポイントです。
リーダーシップにおける評価が低い場合は、マネジメントに力が偏っていないかを確認するようにしましょう。逆も然りで、リーダーシップのみが発揮され、マネジメントが追いついていないケースもあります。
両面で適切な評価を得られるようにバランスをとりながら、目標設定を行うようにしましょう。
目標設定のコツについては、下記の記事で解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
»目標設定しても社員のモチベーションが上がらない理由とは?目標達成のコツと注意点
セミナーや研修に参加する
セミナーや研修に参加することは、現代のビジネス環境で必要な最新知識や実践的スキルを身につけるために有効です。
業界の最前線で活躍する専門家や経験豊かなリーダーから直接情報を得ることができ、講義やグループワーク、ディスカッションなど多様なプログラムを通じて理論と実践の両面を強化できるでしょう。
また、他社や異なる部署の参加者との交流により、新たな視点やアイデアを得られ、自己の成長と組織全体の発展に役立ちます。
得た知識を現場に即応用することで、業務効率の向上やイノベーションの推進にもつながりやすくなります。
定期的なセミナーや研修参加は、変化の激しい環境に柔軟に対応し続けるための重要な投資と言えるでしょう。
どのようなセミナー・研修に参加すべきか分からない方には、「リーダーズアカデミー」がおすすめです。
10年後も成功し続けるために経営者・リーダーが学ぶべき「組織づくり」の秘訣や、リーダーシップ・マネジメントなど、経営者が身につけるべきスキルについて学べます。
53,000人の経営者・リーダーを見てきたからこそ分かる、リアルな「成功の型」をお伝えしていますので、ぜひチェックしてみてください。
» リーダーズアカデミー|10年後も成功し続ける社長の「人と組織の育て方」
リーダーシップとマネジメントスキルを高めた成功事例

組織が持続的に成長し、変革を遂げるためには、リーダーシップとマネジメントの両方のスキルが欠かせません。ここでは、各企業が実践している成功事例を取り上げ、その背後にある戦略や取り組みから得られる学び、さらには具体的な応用方法について詳しく解説します。
先述したようなスキルの伸ばし方を見ても、なかなかイメージが掴めないという方は、ぜひ参考にしてみてください。成功事例は単なる成功ストーリーではなく、現場で実際に役立つ手法や考え方が詰まっており、今後の組織運営の参考になるヒントが多数含まれています。
組織がどのように内外の課題に取り組み、リーダーシップとマネジメントの両方を磨いてきたのか、その実践的な側面を見ていきましょう。
スターバックスにおけるリーダーシップの事例
スターバックスの成功は、企業理念として掲げる「お互いに心から認め合い、誰もが自分の居場所と感じられる文化」に基づくリーダーシップの実践に大きく支えられています。同社はサーバントリーダーシップを徹底し、上司と部下の垣根を超えた相互尊重の風土を築いているのが特徴です。
また、元社長ハワード・ビーハー氏も、リーダー自身が率先して支援する姿勢が、従業員の自発性や創造性を引き出す原動力となっていると明言しています。
具体的には、定期的な研修やフィードバック制度を活用し、全従業員が自己成長できる環境を整備しました。結果、従業員は自らの役割を再認識し、顧客に対しても常に高いホスピタリティを発揮できるようになりました。
また、現場からの意見を経営戦略に反映する仕組みが、コミュニケーションの活性化と組織全体の一体感を育みます。
スターバックスの事例から学べるのは、明確なビジョンとそれに基づく徹底した人材育成、そして従業員一人ひとりの意見を尊重する姿勢が、組織の長期的な成功に不可欠であるという点です。
これらの取り組みは、多くの企業が自社に応用する時の具体的な手法として参考になるものです。
星野リゾートにおけるマネジメントの成功事例
星野リゾートは、経営難に陥っていた老舗旅館の再生に成功したことで注目されています。その背景には、従来の管理手法に固執せず、現場の情報を迅速に活用する「仮説思考」に基づく柔軟なマネジメントがあります。
具体的には、伊東温泉の「湯の宿 いづみ荘」の再生事業において、星野社長は従業員を集め、顧客調査を徹底的に実施しました。得られたデータから、リピーターの中で特に熟年女性が重要な役割を担っていることに気づき、新たなコンセプト「熟年女性のマルチオケージョン(いつ誰と来ても満足できる)温泉旅館」を打ち出すことになります。
このコンセプトのもと、従来のオペレーションを見直し、サービス内容や料理の改訂を行うことで、客室稼働率は大幅に改善されました。
さらに、現場スタッフとの密な連携と、仮説を迅速に検証・修正するプロセスが、問題解決と迅速な意思決定を可能にしました。
星野リゾートの事例からは、情報収集と現場の声を重視するマネジメント手法、そして迅速な仮説検証のプロセスが、組織再生と持続的成長に如何に寄与するかという重要な学びが得られるでしょう。
これらの実践的なアプローチは、他の企業が経営課題に直面した時にも、柔軟に対応するために役立ちます。
リーダーシップとマネジメントの違いを理解してさらなる成長を

本記事では、組織が持続的に成長し続けるために必要なリーダーシップとマネジメントの違い、そしてそれぞれのスキルをどのように高めるかについて詳しく解説してきました。
リーダーシップは、未来へのビジョンを示し、組織全体に情熱と方向性を与える力であり、従業員一人ひとりが自発的に動くための基盤を築きます。
一方、マネジメントは、具体的な計画や目標設定、日々の業務運営を効率的に行うための実行力として、組織の安定した運営を支える重要なスキルです。両者は互いに補完し合い、どちらか一方だけでは組織の成長は実現できません。
例えば、スターバックスの事例では、サーバントリーダーシップによる相互尊重の文化が従業員のモチベーション向上に寄与し、星野リゾートの成功事例では、仮説思考を取り入れた柔軟なマネジメントが問題解決を迅速に行う原動力となりました。
これらの成功事例から学べるのは、リーダーシップとマネジメントのバランスこそが、組織全体のパフォーマンスを最大限に引き出すものであるという点です。
組織がさらなる飛躍を遂げるためには、内部からのフィードバックを活かし、ビジョンと具体的タスクの両面を意識した運営が不可欠です。そして、そのための具体的な手法や実践例を知り、身につけることが重要となります。
リーダーシップとマネジメントの違いを深く理解し、組織づくりのノウハウを学びたい方は、ぜひ「リーダーズアカデミー」をお試しください。
» リーダーズアカデミー|10年後も成功し続ける社長の「人と組織の育て方」
【監修】
黒田 訓英
株式会社 ビジネスバンク 取締役
早稲田大学 商学部 講師
中小企業診断士
早稲田大学商学部の講師として「ビジネス・アイデア・デザイン」「起業の技術」「実践起業インターンREAL」の授業にて教鞭を執っている。社長の学校「プレジデントアカデミー」の講師・コンサルタントとして、毎週配信の経営のヒント動画に登壇。新サービス開発にも従事。経営体験型ボードゲーム研修「マネジメントゲーム」で戦略会計・財務基礎を伝えるマネジメント・カレッジ講師でもある。
日本証券アナリスト協会認定アナリスト(CMA)。日本ディープラーニング協会認定AIジェネラリスト・AIエンジニア資格保有者。経済産業大臣登録 中小企業診断士。