経営者にとって、社員が生き生きと仕事に取り組めている環境は理想的といえます。社員同士のコミュニケーションが円滑になったり、仕事のやりがいを感じてもらったりするためには、「組織の活性化」が有効です。
ただし、組織の活性化は普段聞き慣れない言葉であるため、下記のような疑問を抱える方もいるでしょう。
- 組織の活性化とはどのような状態か
- 組織の活性化によって得られる効果
- 組織を活性化させるための事例
本記事では組織の活性化の具体例とともに、企業で取り入れられている詳しい事例も解説します。ぜひ自社の組織活性化を実現するためにお役立てください。
組織の活性化とは

組織の活性化とは、社員一人ひとりが会社のビジョンに共感し、主体性を持って行動している状態を指します。
| 組織が活性化している状態 | 組織が活性化していない状態 |
|---|---|
| ・社員が会社のビジョンに共感している ・社員同士のコミュニケーションが活発である ・社員が主体性を持ち、生き生きと働いている | ・会社のビジョンが浸透していない ・コミュニケーションが取りづらく風通しが悪い ・社員間の業務に偏りがあり、目的意識がないまま仕事をしている |
組織の活性化は、社員が忙しく働いている状態と混同されがちですが、ポイントは稼働量ではなく、社員に会社のビジョンが浸透しているかどうかです。会社が目指す未来の実現に向けて密に連携を取り合った結果、社員が活発に働いている状態は、組織の活性化が実現できているといえます。
また組織が活性化すると、自身の行動が会社にどう役立つのかを把握できる社員が増えるため、自ずと生産性も上がりやすくなります。
以下の記事では、会社を成長させるための組織づくりの基礎をまとめていますので、組織づくりに悩みを抱えている方はぜひ参考にしてください。
組織の活性化に必要な3つの要素

組織の活性化に必要な要素は、以下の3つです。
| 要素 | 概要 |
|---|---|
| 共通認識 | 社員一人ひとりが会社のビジョンを正しく理解している |
| 貢献意欲 | 各々の役割が明確で、自身の行動がどのようにして会社の利益につながるのか理解している |
| 社員間のコミュニケーション | 風通しが良く、社員間・部門間のコミュニケーションが活発に行われている |
上記3つの要素は「バーナードの組織の3要素」と呼ばれ、組織が機能するうえで必要不可欠な要素であり、1つでも欠けてしまうと組織不全に陥ると言われています。
各項目について、以下の章で深掘りしていきます。
要素その1:共通認識
組織の活性化において、会社の経営理念やビジョンに対する共通認識を社員が持つことは必要不可欠です。正しい認識を持つことで、社員一丸となって共通のゴールを目指せます。
一方、会社のビジョンを理解できていないと、目的意識が芽生えにくくなります。自身の行動が会社にどのような成長をもたらすのかイメージしにくいため、やる気ややりがいが感じられず悪循環です。
明確なビジョンのもと仕事を進められるとやりがいも感じられ、自ら率先して仕事に取り組む社員が増えやすくなるため、組織が活性化します。
なお、社員が会社のビジョンに対する共通認識を持つためには、当然ですが会社のビジョンが明確でなければなりません。そして、明確に定めたビジョンを社員に浸透させることも経営層の役割です。
要素その2:貢献意欲
社員に貢献意欲があると、会社の利益になることを社員が率先して考え行動するようになり、組織が活性化します。貢献意欲を向上させるためには、社員一人ひとりが自身の役割を自覚していることが望ましいです。
そのためには、各部署が会社の利益にどう関わっているのかを説明し、社員の仕事に対する理解を深める必要があります。
また、各社員や部署が達成した成果を社内で共有したり、社員の努力を適切に評価したりする体制も整えておきましょう。
自身の行動が正しく評価されれば、自ずと貢献意欲が芽生えるため、会社に貢献すべく行動する社員が増えやすくなります。周囲の社員にも良い影響を与えてくれるため、好循環が生まれます。
要素その3:社員間のコミュニケーション
社員・部門間の風通しを良くし、コミュニケーションを取りやすい環境を提供することで、組織の活性化が図れます。
より良いサービスを作るためには、社員同士でコミュニケーションを取る必要があります。
アイデアを商品化するためにチームを動かしたり、他部門に協力を仰いだりすることは、コミュニケーションが取れなければ成り立ちません。社員と役職者で定期的にコミュニケーションを取る機会を設けたり、部門間の交流の場を設定したりするなど、社員同士の接点を増やす工夫が必要です。
組織が活性化している状態とは

組織が活性化している具体的な状態は以下の4つです。
- 社員が主体性を持っている
- 社員が会社の理念・ビジョンを理解している
- コミュニケーションが円滑に行われている
- 高い生産性が確保されている
本章では各項目について詳しく説明します。
社員が主体性を持っている
組織の活性化により、社員が主体的に行動するようになります。具体的には、指示を待つだけのような受け身の社員が減り、会社のビジョンを達成すべく自身で考えて行動する社員が増える点が大きな特徴です。
主体性を持った社員が増えると、サービスに関する新たなアイデアが生まれやすくなったり、積極的に業務プロセスを改善して効率化を図る動きが活発化します。会社にとって好循環が生まれ、成長速度の加速も期待できます。
社員が会社の理念・ビジョンを理解している
組織が活性化している状態は、社員が会社の理念やビジョンを理解し、共感していることが前提です。
会社の理念・ビジョンには、サービスを通してどのような人を助けたいのか、どのような社会を作っていきたいのかといった思いが詰まっています。全社員に会社の理念やビジョンを浸透させ、共感を得ることで、初めて組織は同じ目的を持って進めます。
目的を意識して生き生きと働いてもらえるよう、理念・ビジョンの共有は必ず行いましょう。
コミュニケーションが円滑に行われている
社員間・部門間の風通しが良く、積極的にコミュニケーションを取れている状態は、組織が活性化しているといえます。社員間のコミュニケーションが円滑に取れる関係性であれば意見交換がしやすいため、新しいアイデアも生まれやすいです。
また、業務内容や人間関係に悩む社員がいた場合でも相談しやすい環境となるため、ストレスを抱えにくくなります。
さらに、部門間の連携が必要な新施策においても、コミュニケーションが取りやすい環境であれば即座にチーム編成が可能なため、スピード感を持って施策を進められます。コミュニケーションを取りやすい環境の構築は、組織の活性化につながることを覚えておきましょう。
高い生産性が確保されている
活性化した組織は、生産性が高い特徴があります。社員間や部門間でコミュニケーションを頻繁に取っていると認識の相違が起こりにくいため、連携不足によるトラブルが起こる確率が低下します。
また、万が一トラブルが起こった場合でも即座に連携ができるため、素早い対処が可能です。密に連携を取ることでトラブルに対応する時間が減り、結果的に生産性の高い組織が形成できます。
さらに、組織が活性化していると主体性を持った社員が増えるため、業務の効率化が進みやすいです。現状の分析をして無駄を省き、会社の生産性を上げる取り組みが活発になるため、高い生産性が確保できます。
組織の活性化によって得られる効果

組織の活性化によって得られる主な効果は以下の3つです。
- 離職率の低下
- 顧客満足度の向上
- 売上の向上
組織の活性化は社内の環境改善に大いに役立ちますが、同時に顧客の満足度も高められる側面があります。本章では組織の活性化がもたらすメリットや効果を解説していきます。
効果その1:離職率の低下
組織の活性化は、離職率を下げる効果があります。組織が活性化されていると、社員間や部門間での連携が容易になり、コミュニケーションを積極的に取れる環境下で仕事ができます。
頻繁にコミュニケーションを取ることで、会社の仲間と同じゴールを目指して仕事をしている感覚が芽生えやすい点が大きなメリットです。一丸となって仕事に取り組むことでやりがいを感じ、結果的に離職率の低下に繋がります。
一方、組織が活性化されていないと、社員間でコミュニケーションを取る回数が減ってしまいます。連携不足によって個々で動く社員が目立つと、チームで同じ目標を掲げて進むことは困難です。
結果、仕事にやりがいを感じにくくなり、離職につながる可能性が高まってしまうため注意しましょう。
効果その2:顧客満足度の向上
組織の活性化は、自社の社員だけでなく顧客の満足度を向上させることが可能です。組織の活性化によって社員は仕事にやりがいを感じやすくなり、自社のサービスをさらに普及させ、より多くの顧客の悩みを解決したいと思うようになります。
多くの悩みを解決するためにはサービスの改良を進める必要があるため、顧客の意見を積極的に取り入れたり、部門間で意見交換を重ねたりして、サービスの質向上に努めます。結果的により良いサービスのリリースができ、顧客満足度の向上に繋がるのです。
効果その3:売上の向上
組織の活性化によって顧客の満足度が上がれば、自ずと売上も向上します。
顧客の満足度は、サービスを利用した際に顧客が感じる満足感のことです。前述のとおり、より多くの顧客の悩みを解決すべく工夫して作られたサービスは、顧客満足度の向上に役立ちます。
顧客満足度の高いサービスは顧客間でも共有されやすく、より多くの顧客の元へサービスを普及させ、売上が向上します。
ポイントは、初めから売上向上を目的とした施策を考案したわけではない点です。組織の活性化によって主体性を持った社員同士で、顧客の悩みを解決したいと考えた結果、より良いサービスのリリースにつながり、売上向上にもつながったことに意味があります。
上記のように、組織の活性化は社内にのみ効果をもたらすものと思われがちですが、社外にもより良い効果をもたらす施策でもあります。
組織を活性化する方法

本章では、組織を活性化させる3つの要素を満たす方法を紹介します。
- 社員の当事者意識を高める(社員間のコミュニケーション)
- 社員のモチベーションを管理する(貢献意欲)
- 会社の理念を浸透させる(共通認識)
詳しい方法については各項目で解説しているため、ぜひ参考にしていただき、自社の施策として取り入れてみてください。
社員の当事者意識を高める
社員の当事者意識を高めるには、以下3つの方法が有効です。
- 主体性を持って行動できる目標を設定する
- 社員のアイデアを積極的に取り入れる
- 部下の行動を褒める
社員の当事者意識を発揮させるためには、主体的な行動をしっかり認め、積極的に褒めてあげることが理想です。なお、当事者意識を高めることは、バーナードの組織の3要素のうち「社員間のコミュニケーション」に該当します。
主体性を持って行動できる目標を設定する
社員の目標設定をする際、自ら主体性を持って行動できるような目標を最低1つは組み入れましょう。
例えば、自らメンバーとコミュニケーションを積極的に取ることや、仕事の計画を立てて実行し自身で振り返りをするなど、様々な目標設定が可能です。目標設定することで、具体的にどのような行動を取るべきか明確になるため、イメージが湧きやすく達成もしやすくなります。
また、部下が主体的な行動を取り入れた明確な目標設定をすることで、上司も普段の行動から部下を評価しやすくなります。
そして、目標設定の段階から上司と部下で内容を確認しつつ進めることで、万が一お互いの「主体性」に関する認識に相違があった場合でも、事前にすり合わせが可能です。
社員のアイデアを積極的に取り入れる
ミーティング時に社員から出たアイデアは、積極的に取り入れましょう。
主体的な行動を取りやすい環境は、チャレンジしやすい環境ともいえます。役職に関わらずアイデアが採用されることが伝わればチャレンジもしやすくなり、ミーティングで社員が主体的な行動を取りやすくなります。
一方で、ミーティングで出したアイデアがなかなか採用されないと、社員のやる気を削いでしまい、主体的な行動を控える原因になりかねません。
まずはアイデアを出してくれたことを認め、かつ実現可能であれば積極的に採用することを意識しましょう。また、実現できる可能性が少しでもある場合は、部下と一緒にアイデアをブラッシュアップすることも効果的です。
部下の行動を褒める
部下の行動に着目し、主体的な行動だと感じた場合は積極的に褒めましょう。行動の結果に関わらず、まずは主体的な行動をしたことを認めて褒めてあげると、次回からもチャレンジしやすくなります。
また組織の活性化には社員間のコミュニケーションが必要不可欠なため、褒めることを意識すると、上司と部下の間でも自然にコミュニケーションが取れるようになります。
なお、行動に対するフィードバックも必要があればすべきですが、先に褒めることを忘れずに行いましょう。
以下の記事では、主体的に動き、成果を出す部下の育て方を解説しています。部下の育成に悩む方はぜひ参考にしてください。
社員のモチベーションを管理する
社員のモチベーション管理に大切なポイントは以下の3つです。
- メンターをつける
- 目標設定は達成できる内容にする
- 適切な人員配置を行う
組織の活性化は、社員のモチベーションとも強い関わりがあります。本章で理解を深め、モチベーションを保ちつつ仕事に取り組めるようにしましょう。なお、モチベーションを管理することは、バーナードの組織の3要素のうち「貢献意欲」に該当します。
ポイントその1:メンターをつける
メンター制度とは、先輩がメンターとなり、部下に助言することです。メンターとなった社員は担当する部下の状況を確認し、適切なタイミングでコミュニケーションを図ることが求められます。
メンター制度のメリットは、社員の異変をいち早く察知でき、モチベーションが低下している状態を放置してしまうリスクを防げることです。仕事がうまく進んでいなさそうなときや悩みを抱えている場合など、部下の些細な変化に気付くため積極的にコミュニケーションを取るようメンターを指導しましょう。
また、メンター制度を通して普段からコミュニケーションを取ることで、気軽に相談しやすい関係を構築できます。社員のモチベーションを維持し、生き生きと仕事ができる環境をサポートすることで、組織の活性化につながります。
ポイントその2:目標設定は達成できる内容にする
目標設定は、達成できる範囲で行うことが大切です。高い目標を掲げることは大切ですが、万が一達成できなかったとき、モチベーションが低下しやすいデメリットがあります。
組織の活性化を推進するうえで、社員のモチベーション低下は大敵です。あまりにも高い目標は避け、努力をすれば達成できそうな範囲で設定できるようにしてください。
なお、適切な難易度で目標設定をする際は「ストレッチゾーン」を参考にしましょう。ストレッチゾーンとは目標の難易度を示す指標の1つです。
| 目標の難易度 | モチベーションへの影響 | |
|---|---|---|
| パニックゾーン | 高すぎる難易度と過度なプレッシャーにより、多大なストレスがかかる | 自信を喪失し、モチベーションは低下する |
| ストレッチゾーン | 適度な難易度で、努力次第で達成可能なため成長意欲が促進される | モチベーションは向上する |
| コンフォートゾーン | 現状のままでも十分に達成が可能 | 現状に満足してしまっている状態で、モチベーションは停滞する |
上記のように、ストレッチゾーンは適度な難易度かつ努力次第で到達可能なため、モチベーションが上がりやすい特徴があります。
ただし、難易度が低い場合は現状に満足し、高すぎる場合には過度なストレスがかかるため、ストレッチゾーンを参考に適切な難易度で目標の設定をしましょう。
また、部下の目標設定が完了したら、メンターや上司も必ず目を通すようにしましょう。目標のレベルを判断し、達成可能な目標に切り替えることで、部下のモチベーションが維持しやすくなります。
以下の記事では、目標設定のコツや達成するポイントを解説しています。適切な目標設定ができているか確認する際にぜひ参考にしてください。
» 組織の目標とは?立て方や重要性、設定のコツと達成するポイントも解説
ポイントその3:適切な人員配置を行う
社員のモチベーションを維持するためには、適切な人員配置をすることが大切です。
人間関係は、組織の活性化に重要なポイントですが、モチベーションを下げる原因の1つにもなる要素です。自身が得意な分野であったり、好きな仕事に携われたりしていても、人間関係が良好でなければモチベーションの維持は難しくなります。
そのため、社員同士の相性が悪いなど、人員の配置が適切でないと判断できる場合は、人員配置を考え直しましょう。
会社の理念を浸透させる
会社の理念を浸透させるためには、以下3つの方法が有効です。
- 理念に関する研修の機会をつくる
- 理念を体現した行動指針を全社員で考える
- 経営層が行動指針に沿った行動を取る
組織の活性化には、会社の理念の浸透は必要不可欠です。社員が同じ方向を向いて日々の仕事に取り組めるよう、本章で理解を深めましょう。なお、会社の理念を浸透させることは、バーナードの組織の3要素のうち「共通認識」に該当します。
方法その1:理念に関する研修の機会をつくる
会社が掲げる理念に対する正しい認識を社員に持ってもらうために、研修をしましょう。
なお、研修は各社員が入社するタイミングで行うことをおすすめします。研修時は、理念を考えた経営幹部陣が説明すると、会社設立時の思いが伝わりやすいです。
また理念が生まれた経緯や、会社がビジネスを通して実現したい未来を話すと、理念に対する社員のイメージが湧きやすくなります。社内で理念を共有することで、会社が目指すゴールに対する共通認識を持てるため、組織の活性化の促進ができます。
方法その2:理念を体現した行動指針を全社員で考える
理念を社員に共有したあとは、理念を体現した行動を明確に説明しましょう。理念に対する正しい認識を持つことも大切ですが、一番重要なのは経営理念を自らの行動で体現することです。
「どのような行動が理念を体現しているのか」が明確になっていないと、理念はわかっていても、どのように体現したら良いか社員には伝わりません。理念を体現する行動が明確に示されている場合は社員が主体的に行動しやすくなり、理念もより浸透しやすくなります。
理念を体現した行動の明確化には「クレド」の作成がおすすめです。クレドとは、「企業が掲げる経営理念を社員が体現するための行動指針」です。

なお、幅広い部門の社員同士でプロジェクトチームを編成してクレドの作成を進めていくことで、企業全体で行動指針が浸透しやすくなります。クレドの作成手順は以下のとおりです。
- クレドを作成する目的の明確化
- クレド作成のプロジェクト立ち上げ
- プロジェクトメンバーの選出
- 社内アンケートやヒアリングの実施
- 経営層と認識のすり合わせ
- クレドを文章で表す
クレドの作成と文章化が完了したら、カードを作成して社員に配布したり、オフィス内に掲示したりすることで、全社員に行動指針が浸透していきます。社員の目に入りやすい場所に、作成したクレドを掲げておくことが理想的です。
方法その3:経営層が行動指針に沿った行動を取る
理念の浸透には、理念を考えた経営陣が自ら体現することも大切です。経営層が理念に沿った行動を取ることで社員の模範となり、理念への理解を深める手助けになります。
反対に、経営層が理念を無視した行動を取ってしまうと、社員に理念の重要性が伝わりません。認識を深めてもらうためにも、口頭での説明だけでなく、行動でも社員に理念の重要性を示せるようにしましょう。
社員一同で作成したクレドに沿った行動を、経営層が積極的に取っていくことが理想的です。
以下の記事では、経営理念を社内で浸透させるためにやるべきことをまとめています。社員に対して経営理念の浸透が進んでいない場合や、詳しい方法がわからない方はぜひ参考にしてください。
» 経営理念を掲げるだけでは意味がない?社員が真の意味で理解し、社内で浸透するためにやるべきこと
組織の活性化への取り組み事例

本章では、組織の活性化を目的とした他社の事例を紹介しています。組織の活性化を進めたい場合でも、どのような施策を考えたら良いかわからない方も多いはずです。
以下で紹介する事例を元に、自社で取り組めそうなアイデアを取り入れてみましょう。
事例その1:株式会社ぐるなび
株式会社ぐるなびでは、社員のコミュニケーションを活発にすることを目的とした施策である「ウォーキング・ミーティング」を実施しています。皇居周辺を歩きながら社員とミーティングをする取り組みとして、社内で定着しているようです。
歩きながらのミーティングは、第三者に邪魔されず集中できるため、アイデアを思いつきやすいメリットがあります。
また、会議室とは違いオープンな環境で話すため、リラックスしながら話ができる点も大きなメリットです。運動不足も解消しつつ、有意義なミーティングができるため、一石二鳥の施策として注目されています。
事例その2:株式会社資生堂
株式会社資生堂では、若手の社員が上司のメンターになる「リバースメンタリングプログラム」を実施しています。
通常のメンター制度では、上司が部下のメンターになることが一般的です。本施策は通常のメンター制度とは逆のものとなり、若手社員は経営陣を相手にコミュニケーション能力を磨き、上司はマネジメントされる側の理解ができるメリットがあります。
メンター制度で求められることは、自身の意志を正確に伝えられるコミュニケーション能力や、相手の気持ちを理解しようとする傾聴力です。あえて逆の立場でメンター制度を行い、相手の視点に立った考え方を養うことが目的です。
引用元:株式会社資生堂
事例その3:カルビー株式会社
カルビー株式会社では、コミュニケーションを活発にすることを目的とした「フリーアドレス制度」を実施しています。
フリーアドレス制度とは、社員ごとに特定の座席を設けず、自由に座れる制度です。フリーアドレスによって部門や世代関係なくコミュニケーションが取りやすくなるため、自身の部門以外にも知り合いが増えるメリットがあります。
別の部門に知り合いが増えることで部門間の隔たりをなくし、風通しも良くすることで連携もスムーズになります。知り合いが増えればコミュニケーションを取る場面も増えやすくなるため、組織の活性化に大いに役立つ施策です。
引用元:カルビー株式会社 カルビー、本社オフィスを全面リニューアル!“畑”をモチーフに、新たな価値やアイデアがより共創しやすい空間へ
組織の活性化によって会社の成長を加速させよう

組織の活性化によって社員は主体的な行動を取り、やりがいを感じながら仕事に取り組めるようになります。高いモチベーションを持った社員は顧客の悩みを積極的に解決しようと努め、顧客満足度の向上や、会社の売上向上も期待できるでしょう。
組織の活性化に必要な要素および具体的な施策を以下にまとめました。
- 共通認識:経営層が社員に理念の成り立ちを共有する
- 貢献意欲:社員の努力を適切に評価できるような目標の設定をする
- 社員間のコミュニケーション:メンター制度の導入や部署間の交流会を開く
組織の活性化は会社の成長には不可欠な要素のため、他社の施策を参考に自社組織の活性化を図りましょう。
会社の成長に欠かせない「組織づくり」を深く学びたい方向けに、リーダーズアカデミー特製の「組織づくり」お役立ち資料をお届けしています。お気軽にお申し込みください。
» リーダーズアカデミー|10年後も成功し続ける社長の「人と組織の育て方」
【監修】
黒田 訓英
株式会社 ビジネスバンク 取締役
早稲田大学 商学部 講師
中小企業診断士
早稲田大学商学部の講師として「ビジネス・アイデア・デザイン」「起業の技術」「実践起業インターンREAL」の授業にて教鞭を執っている。社長の学校「プレジデントアカデミー」の講師・コンサルタントとして、毎週配信の経営のヒント動画に登壇。新サービス開発にも従事。経営体験型ボードゲーム研修「マネジメントゲーム」で戦略会計・財務基礎を伝えるマネジメント・カレッジ講師でもある。
日本証券アナリスト協会認定アナリスト(CMA)。日本ディープラーニング協会認定AIジェネラリスト・AIエンジニア資格保有者。経済産業大臣登録 中小企業診断士。

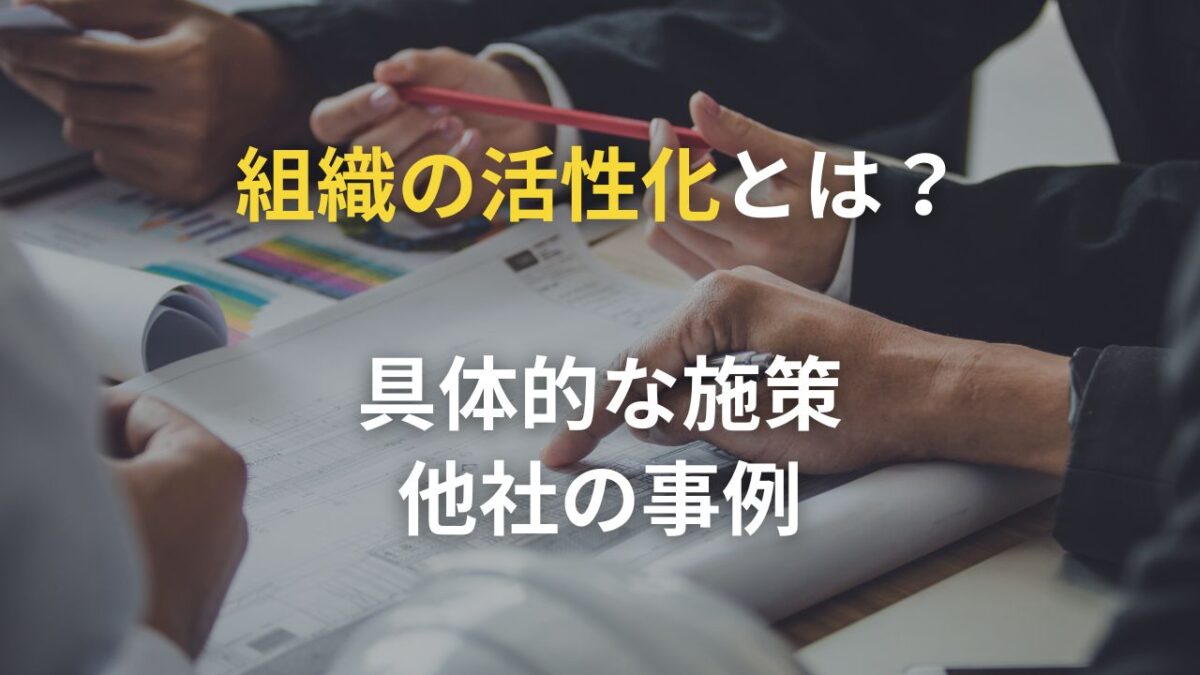




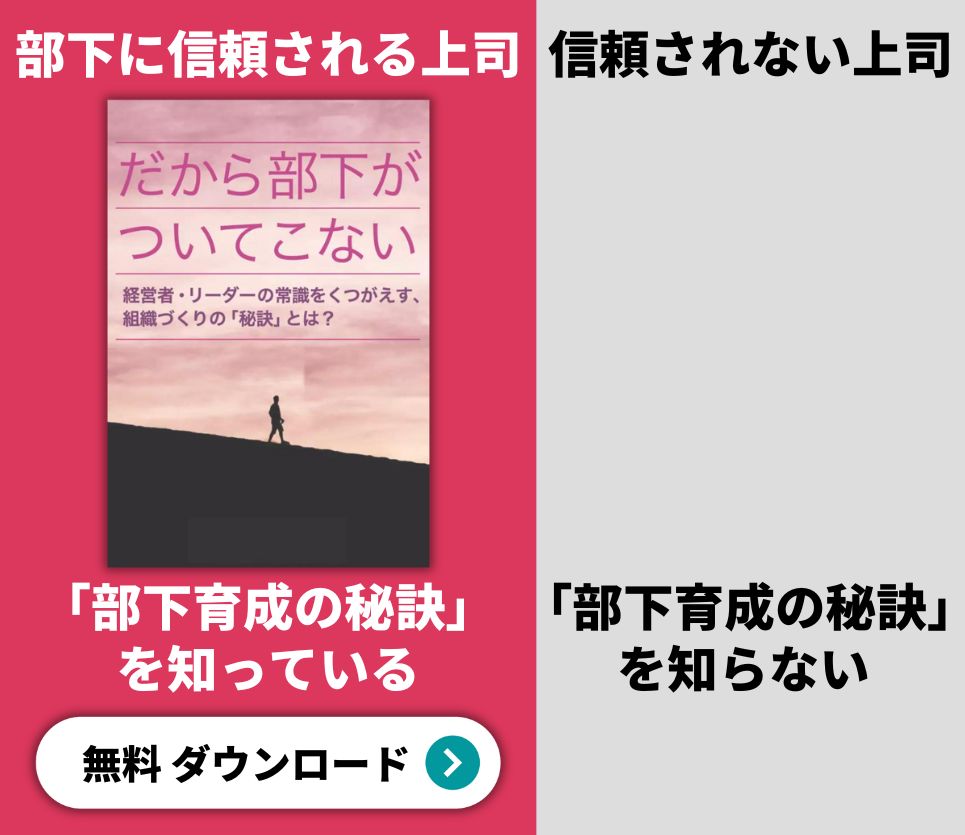
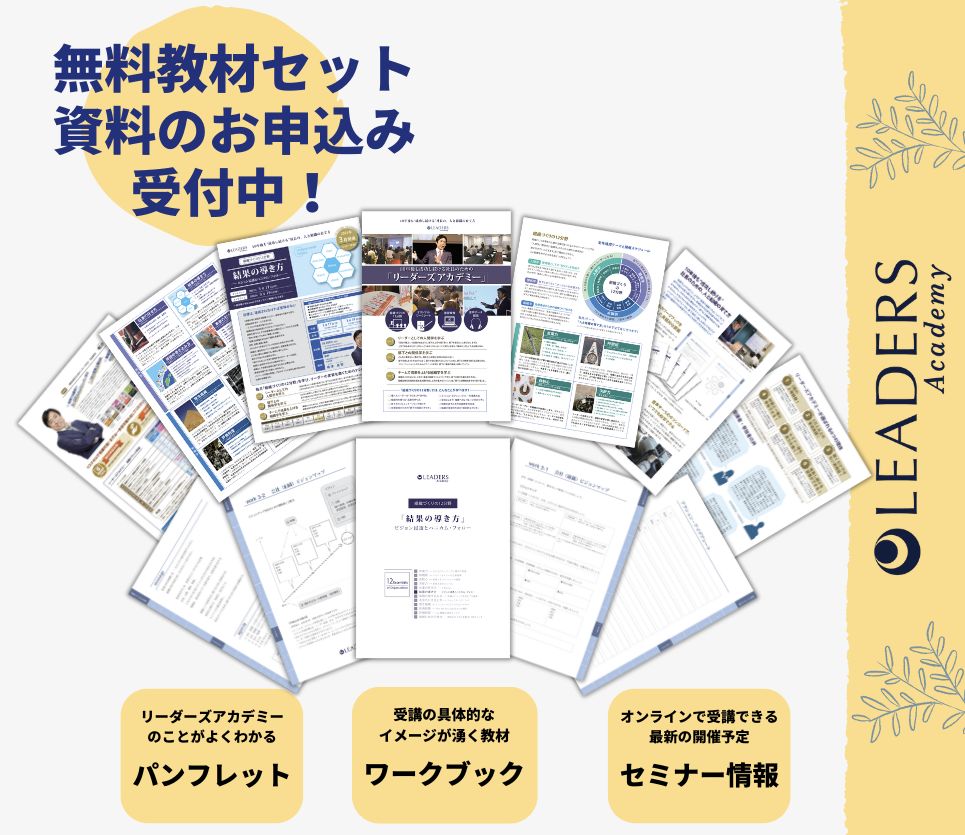
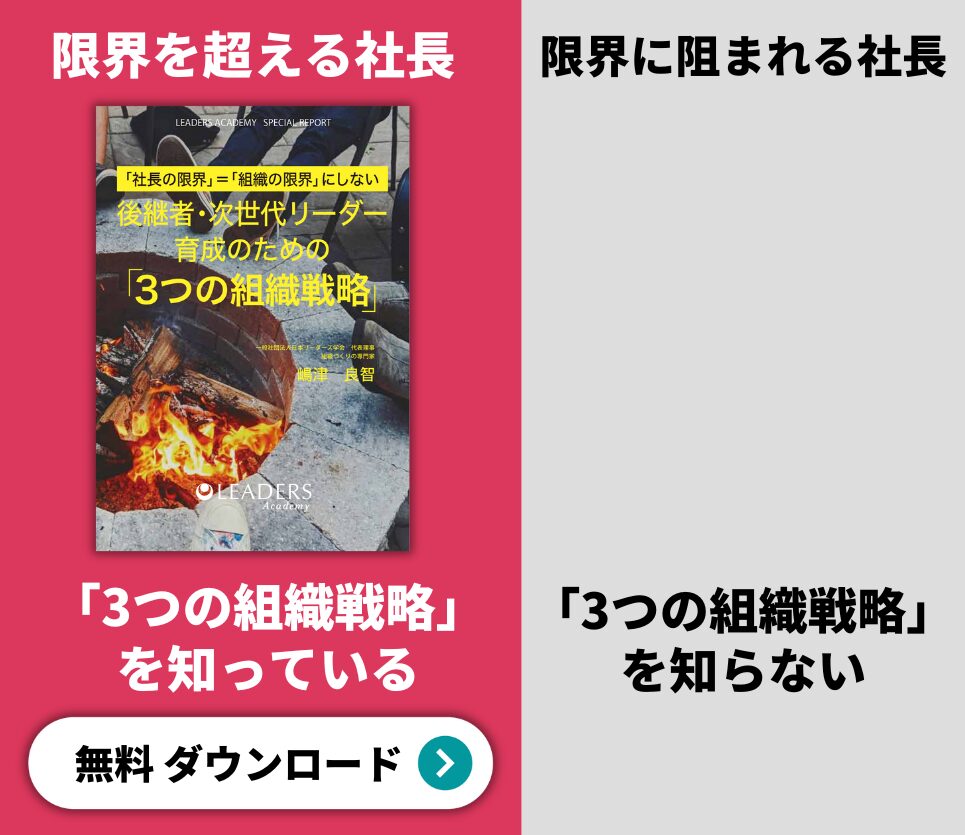
 【無料】「組織づくりの秘訣」
【無料】「組織づくりの秘訣」