組織のコミュニケーションが不足すると、組織全体の生産性が低下したり、離職率の増加につながったりするリスクがあります。そのため、次のような悩みを持つ方も多いでしょう。
- 組織コミュニケーションとは何か、詳しく知りたい
- 組織コミュニケーションを活性化させる方法を知りたい
- 組織コミュニケーションを活性化させるための具体的な施策を知り、実践したい
本記事では、まず組織コミュニケーションとはそもそも何か、どのようなリスク・課題があるのかについて解説します。
その上で、コミュニケーションを活性化させるための具体的なアクションや事例についてもお伝えしますので、ぜひ参考にしてください。
組織コミュニケーションとは
組織コミュニケーションとは、企業や組織内で情報や意見を共有し、目標達成に向けてメンバー全員が連携を取ることを意味します。

具体的には、経営陣から管理職への指示伝達や、現場社員からのフィードバック、部門間の情報共有などがスムーズに行われるようなコミュニケーションのあり方です。
組織コミュニケーションが適切に機能することで、業務効率や生産性が向上し、顧客に安定した品質のサービスや製品を提供しやすい環境を整えられます。
さらに、組織コミュニケーションの活性化は、単に情報の伝達を円滑にするだけでなく、社員一人ひとりのエンゲージメントやモチベーションを高め、職場の雰囲気を向上させる効果もあります。
例えば、部門間の壁を取り払い、共通の目標を共有するような仕組みが整うと、チーム全体がより協力的に取り組めるでしょう。
組織コミュニケーションを機能させるためには、経営陣と社員が対話しやすい文化やツールを整備することが重要です。意思疎通が効果的に行える環境を整えることで、組織全体の目標達成がスムーズになります。
組織づくりに対して悩みがある方は、こちらの記事を参考にしてください。
» 組織づくりとは?企業を成長させる「強い組織」の作り方 | リーダーズアカデミー
組織コミュニケーションが重要な理由
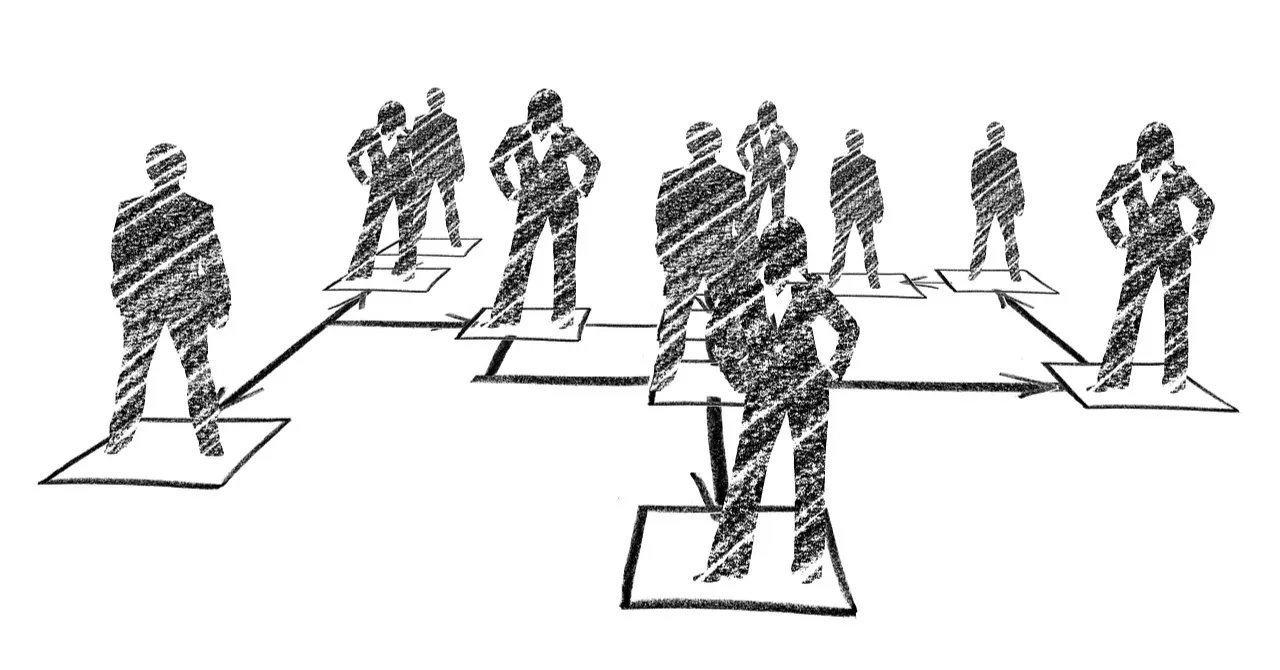
組織コミュニケーションが重要な理由としては、以下の3つが挙げられます。
- 組織の目標やミッションを共有できる
- 情報共有がスムーズになる
- 雰囲気の良い組織づくりができる
以下では、組織コミュニケーションが重要とされる理由について、それぞれ詳細をお伝えします。
理由その1:組織の目標やミッションを共有できる
組織全体で適切なコミュニケーションを取ることで、目標やミッションをメンバー全員に共有しやすくなります。社員一人ひとりが自分の役割や業務の意義を理解しやすくなり、目標達成に向けた意識が高まるでしょう。
例えば、全社ミーティングや社内報を通じて目標を共有したり、リーダーが定期的に進捗状況を確認してフィードバックしたりすることで、社員のモチベーションを高めることが可能です。
共通の目標を認識することで、組織全体の連携が向上するため、組織コミュニケーションは非常に重要であると言えます。
組織の目標について詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。
» 組織の目標とは?立て方や重要性、設定のコツと達成するポイントも解説
理由その2:情報共有がスムーズになる
組織コミュニケーションは、情報共有をスムーズにし、業務の効率化を促進させるという面でも非常に重要です。適切な情報共有が行われることで、意思決定が迅速になり、タスクの進行もスムーズになります。
例えば、チャットツールやプロジェクト管理ツールを活用することで、リアルタイムで進捗を共有し、問題を即座に解決できる環境を整えられます。
組織として正確かつ迅速に情報を共有することで、プロジェクトの生産性や成功率を大幅に向上させられるでしょう。
理由その3:雰囲気の良い組織づくりができる
雰囲気の良い職場づくりができることも、組織コミュニケーションの重要な理由です。メンバー同士が積極的に意見を交換しやすい環境は、信頼関係を築く上でも大きなメリットとなります。
例えば、ランチ会や社内イベントなどを定期的に実施することで、社員はリラックスした雰囲気の中でコミュニケーションを図れます。上下関係や部門間の壁が薄れ、協力しやすい環境が生まれるでしょう。
組織が横断的にコミュニケーションを取ることで、人間関係の余計なプレッシャーを感じなくなり、業務に集中して取り組めます。
組織コミュニケーションの不足で生じるリスク

組織コミュニケーションの不足には、主に3つのリスクがあります。
- 生産性が低下する
- コンプラ違反や不正行為につながる
- 離職率増加につながる
これらのリスクは最終的に会社の業績にも影響を与える部分であり、極力避けることが望まれます。以下で詳しく解説しますので、ぜひチェックしてみてください。
リスクその1:生産性が低下する
組織内のコミュニケーションが不足すると、情報が適切に共有されず、生産性が悪くなるリスクがあります。具体的には、タスクの進捗が遅れてプロジェクトの締切に間に合わなかったり、重複作業が発生して無駄が増えたりなどの懸念があるでしょう。
例えば、営業部門が技術部門に顧客ニーズを正確に伝えられず、結果として顧客の期待と異なる製品やサービスが提供されるケースがあります。このような問題は、組織全体の生産性を低下させ、業績にも悪影響を及ぼす可能性があるでしょう。
リスクその2:コンプラ違反や不正行為につながる
コミュニケーションが不足している組織では、社員同士の関心が薄れ、コンプラ違反や不正行為が発生しても見過ごされる可能性が高まります。社員が意見を出しづらい環境では、問題を早期に指摘することが難しく、企業の信頼性を損なう結果につながるでしょう。
特に管理職が現場の声を十分に聞かないことで、違法行為や倫理的に問題のある行為が見逃され、後になって大きな問題として浮上するケースが挙げられます。コンプラ違反や不正行為を予防するためにも、組織コミュニケーションが重要となります。
リスクその3:離職率増加につながる
職場でのコミュニケーション不足は、社員の不満を蓄積させ、最終的には離職率の増加につながります。信頼関係が築けず、社員は自分の意見が軽視されていると感じ、組織に対する帰属意識を失う可能性があるでしょう。
例えば、定期的なフィードバックや相談機会が設けられない場合、社員は仕事の方向性やキャリアパスに不安を感じやすくなります。その結果、優秀な人材が組織を離れる原因となり、組織の競争力が低下する恐れがあります。
組織コミュニケーションでよくある課題や懸念点

組織コミュニケーションは欠かすことのできないものですが、いくつかの課題や懸念点も見られます。具体的には、次の3つのような課題が考えられるでしょう。
- 情報共有が不十分
- 部門間の連携が悪い
- コミュニケーションツールが定着しない
ここでは、各課題について詳細を解説し、どのように対処すべきなのかをお伝えします。
課題その1:情報共有が不十分
よくある課題の1つとして、情報共有が不十分なことが挙げられます。
情報共有が適切に行われていない場合、進捗状況に遅れが出たり、重要なタスクの見落としが発生しやすくなったりするなどが懸念されます。業務が停滞し、組織全体の生産性が低下するリスクがあるでしょう。
例えば、プロジェクトの進捗状況を把握する仕組みがないと、関係者が状況を誤解し、不要なタスクが発生する場合があります。
こうした問題を解決するには、社内報の作成や情報共有ツール(Google WorkspaceやSlackなど)の導入を検討することが効果的です。
情報共有の重要性やメリットについては、こちらの記事を参考にしてください。
» 情報共有はなぜ必要?組織における情報共有で生まれる様々なメリットとは
課題その2:部門間の連携が悪い
2つ目の課題としては、部門間の連携が悪く、組織コミュニケーションが取れないケースがあります。
特に部門間で目標や優先事項が共有されていない場合は、連携不足が起きやすくなるでしょう。結果、情報の断絶や業務の重複、顧客対応における認識のズレなどが生じることがあります。
例えば、営業部門が顧客の要求を細かくヒヤリングしたとしても、技術部門との連携が悪ければ情報が正確に共有されづらくなります。このような状態では、「組織としてコミュニケーションが取れている」とは言えないでしょう。
この課題を解決するためには、部門間の壁を超えた横断的なミーティングや共通KPIの設定が有効です。
課題その3:コミュニケーションツールが定着しない
デジタルツールを導入しても、使い方の教育が不十分だったり、運用ルールが整備されていなかったりすると、ツールが十分に活用されずかえって混乱を招くことがあります。
例えば、チャットツール内で私的な会話が増えると、重要な情報が埋もれてしまい、業務効率が下がる場合があります。
他にも、デジタルに不慣れな一部の社員がツールの使用自体に不安を抱え、運用に積極的ではないケースもあるでしょう。
この課題を解決するには、ツールの利用方法に関するトレーニングを実施し、明確な運用ガイドラインを策定することが重要です。
組織のコミュニケーションを活性化する8つの方法

ここまで、組織コミュニケーションの重要性や不足するリスク、よくある課題や懸念点などをお伝えしました。しかし、重要となるのは「組織コミュニケーションを実際にどのように活性化させるのか」という部分です。
具体的な方法としては、次の8つが挙げられるでしょう。
- 1on1ミーティングの開催
- ランチによるコミュニケーション
- 社内アンケートの実施
- 社内イベントの定期開催
- 社内報の作成
- リバースメンタリングの導入
- デジタルツールの活用
- Good & Newの実施
各方法について、詳細をお伝えします。
その1:1on1ミーティングの開催
1on1ミーティングは、上司と部下が1対1で話し合う場を定期的に設ける取り組みです。
このミーティングでは、業務の進捗確認だけでなく、部下の悩みやキャリアに関する意見を吸い上げられます。上司と部下の信頼関係が深まり、社員のエンゲージメントを高める効果があります。
例えば、月に1回15~30分程度の1on1を実施し、現場の声を経営陣にフィードバックする仕組みを構築するのが有効です。
あらかじめアジェンダを用意しておくと、無駄な雑談や双方への余計な負担がかかりにくく、スムーズに実施できるでしょう。
その2:シャッフルランチの開催
ランチタイムは、リラックスした雰囲気でコミュニケーションを図れる絶好の機会です。上司や部下、同僚などがランチを共にすると、普段の業務では見られない一面を知ることで親密な関係を築けます。
例えば、月に一度、異なる部門のメンバーをランチ会に招待する「シャッフルランチ」を導入することで、部門間の連携が強化されるでしょう。
シャッフルランチでは、普段交流の少ない社員同士が3〜5人ほどでランチを共にして、会社負担で実施するのが一般的です。
会社の業績には直接影響しないように思えますが、組織コミュニケーションが活性化し、結果的に生産性の向上や業績へのポジティブな影響につながります。
その3:社内アンケートの実施
社内アンケートは、社員の意見や改善点を把握するための有効な手段です。匿名性を確保することで、社員が自由に意見を述べられる環境を提供できるため、組織コミュニケーションも活性化されます。
例えば、特定のプロジェクト終了後のフィードバックアンケートを実施したり、定期的に実施したりすると、課題が明確になり、具体的な改善策を講じることが可能です。
社員には自分の意見や不満を伝える機会が与えられるため、不満を抱えてモチベーションが下がるような事態も避けやすくなるでしょう。
その4:社内イベントの定期開催
チームビルディングを目的とした社内イベントを開催することで、社員同士の交流が促進可能となり、組織コミュニケーションが活性化されるでしょう。特に、日常業務では接点が少ない異なる部門の社員が交流する場を設けることが効果的です。
例えば、運動会、ボランティアイベントなど、多様な形式のイベントを通じて、社員同士の親密度を高められます。
社内の人間関係が円滑になり、業務での関わり方も改善される可能性が高いです。
その5:社内報の作成
社内報を活用することで、情報共有がしやすくなり、組織のコミュニケーションも活性化できます。
具体的には、組織の現状や目標を共有すると、社員の一体感を高めたり、方向性を再確認したりすることが可能です。他にも、成功事例や社員インタビュー掲載により、他の社員の刺激となり、モチベーション向上につながります。
会社の経営者自らが社内報で意見を述べることにより、リーダーシップを発揮できます。また、優秀なリーダーやリーダー候補の若手社員を取材して紹介すると、社員間での話題が増えてコミュニケーションを取りやすくなるでしょう。
社内報は紙媒体だけでなく、メールや社内ポータルを活用したデジタル版の作成も効果的です。
その6:リバースメンタリングの導入
リバースメンタリングとは、若手社員が上司や役員に最新のトレンドやデジタル技術などについて教える仕組みです。通常のメンタリングとは逆のやり方ですが、上下関係を超えたフラットな対話が生まれ、世代間のギャップを埋める効果が期待できます。
上下関係の壁が薄くなると組織コミュニケーションも円滑になるでしょう。
例えば、月に1度リバースメンタリングのセッションを設け、若手社員が役員にSNSや最新ツールの活用法を指導するプログラムを実施する方法があります。上層部は新しい技術や知識に触れられる意味でも学びとなり、一石二鳥のメリットがあります。
その7:デジタルツールの活用
チャットツールやプロジェクト管理ツールを活用することで、情報共有や意思決定を効率化できます。
具体的には、SlackやGoogle Workspaceなどのツールを活用して、部門間のコミュニケーションや情報共有を円滑にする取り組みが有効です。
ツールの活用により、組織コミュニケーションを活性化させ、組織全体のパフォーマンス向上につなげられます。
その8:Good & Newの実施
Good & Newとは、24時間以内など一定時間におきた「良かったこと(Good)」「新しい発見(New)」を定例などで発表し、社内共有する取り組みです。
テーマは仕事だけでなく、プライベートな出来事も含まれ、リラックスした状態でコミュニケーションを取れるのが特徴です。
例えば、「週末に訪れたレストランが最高だった」や「新しいツールを試してみて効果的だった」など、個人的なことでも気軽に発表できます。
発表した内容がきっかけとなって組織コミュニケーションが活発になったり、社内全体がポジティブな視点で仕事に取り組めるようになるなどのメリットがあります。
組織コミュニケーションの成功事例
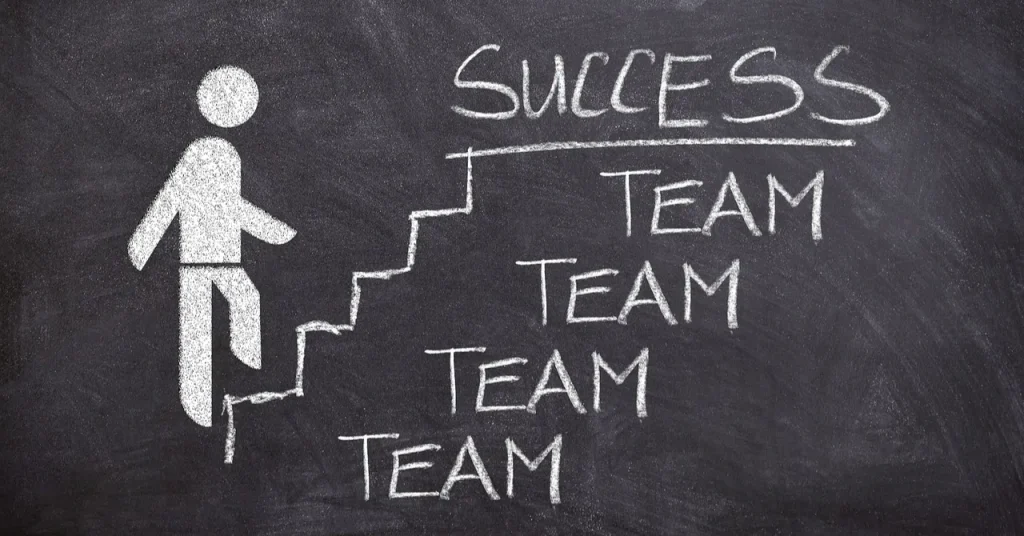
組織コミュニケーションを活性化させる方法は先述した通りですが、他社では実際にどのような取り組みをしているのか気になる方も多いでしょう。
ここでは、次の3つの成功事例をお伝えします。
- 1on1ミーティングの事例
- 社内ランチの事例
- 社内イベントの事例
各事例のやり方を参考にしつつ、取り入れられる部分がないか考えてみてください。
1on1ミーティングの事例
LINEヤフー株式会社では、上司と部下が1対1で対話する1on1ミーティングを積極的に導入しています。週1回(30分目安)で実施しており、仕事の進捗やキャリアに関するフィードバックをする仕組みを整えています。
この取り組みの目的は、部下の意見や悩みを吸い上げ、業務の方向性やキャリアの成長、経験学習などを支援することです。
具体的に同社では、下記2つの目的に重点を置き、1on1ミーティングを実施しました。
- 経験学習による人材育成
- 社員の才能・情熱の解放
単に1on1ミーティングを実施するのではなく、外部の専門家からアドバイスを受けながら実施したのも特徴です。
また、対話を通じて信頼関係を築くことで、社員のエンゲージメントを向上させています。
社内ランチの事例
株式会社ウィルゲートでは、社員間の交流を深めるためにオンラインランチ会を導入しています。入社1ヶ月以内の従業員を対象としており、ロールモデルとなる先輩や上司との気軽な対話ができる環境を整えました。
この取り組みは、特にリモートワークが主流になった時期に効果を発揮しました。リモートワークでは業務上の付き合いのみで、会話をする機会も制限されるため、オンラインランチ会を実施することでカジュアルな話題を共有し、社員間の親睦を深める目的があります。
結果、組織コミュニケーションも円滑となり、業務上のスムーズな連携にもつながりました。
社内イベントの事例
株式会社デンソーでは、社員同士の結束力を高めるために社内運動会を定期的に開催しています。このイベントは、部門間の壁を取り払い、社員全員がリラックスした雰囲気で交流する機会として活用されています。
運動会の競技を通じて自然とチームワークが育まれるだけでなく、普段接点のない社員同士が親密な関係を築けるでしょう。
具体的には、1万4,000人の従業員にて社内運動会の予選を実施し、勝ち残った3,000人が本戦に参加できる仕組みとしました。社員同士で本戦に出るための練習をするなど、業務以外でのコミュニケーションが増えたのが特徴的です。
イベントがきっかけで社員は業務におけるコミュニケーションも円滑になり、組織全体の活性化につながっています。
組織コミュニケーションは生産性向上に欠かせない

組織コミュニケーションは、企業の成長や成功にとって必要不可欠な要素です。本記事で紹介した通り、コミュニケーションが円滑であれば、目標やミッションの共有が容易になり、情報のスムーズな流れや職場環境の改善につながります。
一方で、コミュニケーションが不足すると、生産性の低下や社員のモチベーション低下、離職率の増加といったリスクが発生します。
今回紹介した取り組みや成功事例を参考にして、自社に適した方法を考えてみましょう。
企業を成長させるための「組織の作り方」については、リーダーズアカデミー特製の「組織づくり」お役立ち資料をお届けしています。お気軽にお申し込みください。
» リーダーズアカデミー|10年後も成功し続ける社長の「人と組織の育て方」
【監修】
黒田 訓英
株式会社 ビジネスバンク 取締役
早稲田大学 商学部 講師
中小企業診断士
早稲田大学商学部の講師として「ビジネス・アイデア・デザイン」「起業の技術」「実践起業インターンREAL」の授業にて教鞭を執っている。社長の学校「プレジデントアカデミー」の講師・コンサルタントとして、毎週配信の経営のヒント動画に登壇。新サービス開発にも従事。経営体験型ボードゲーム研修「マネジメントゲーム」で戦略会計・財務基礎を伝えるマネジメント・カレッジ講師でもある。
日本証券アナリスト協会認定アナリスト(CMA)。日本ディープラーニング協会認定AIジェネラリスト・AIエンジニア資格保有者。経済産業大臣登録 中小企業診断士。





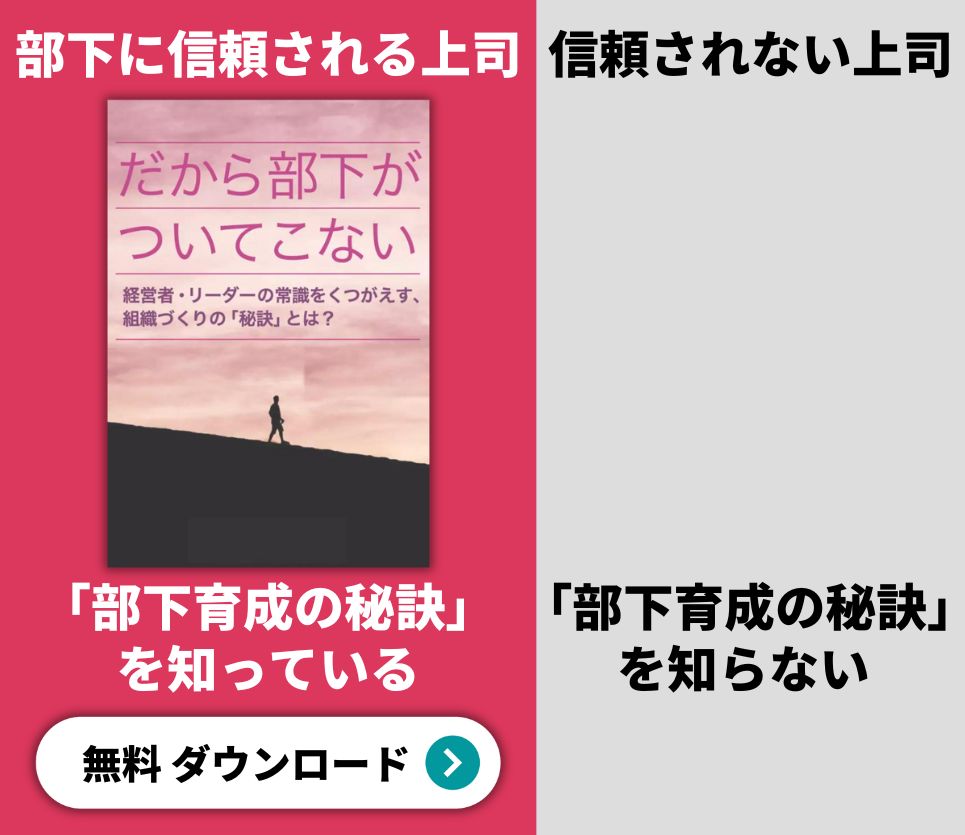
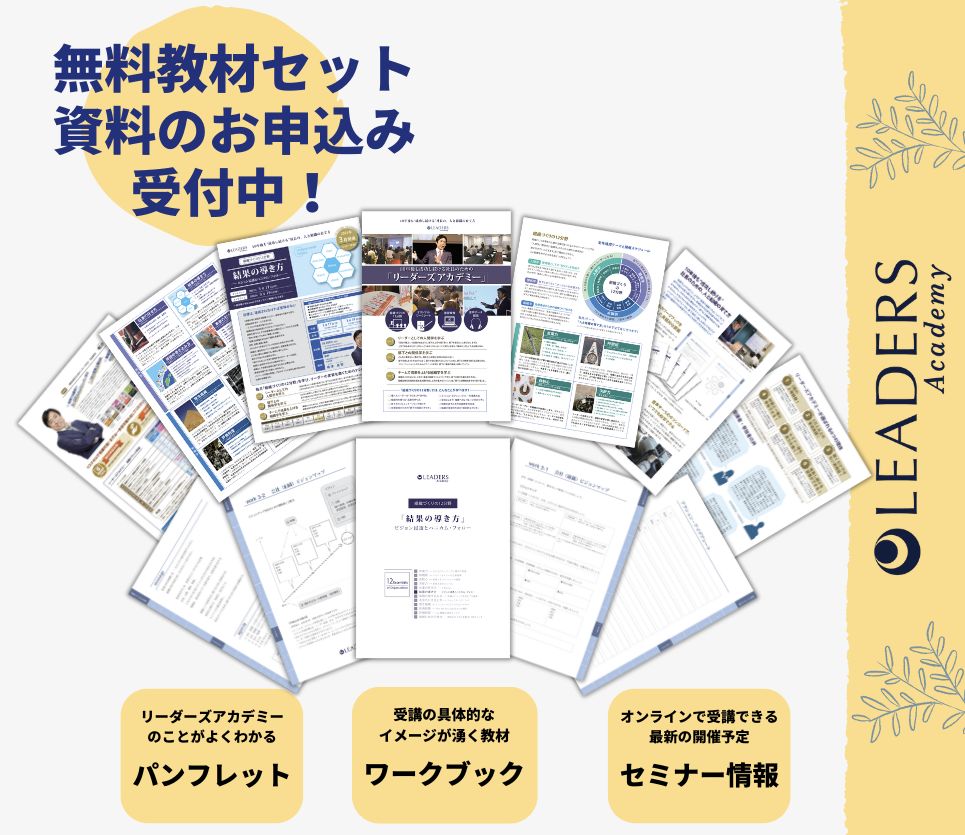
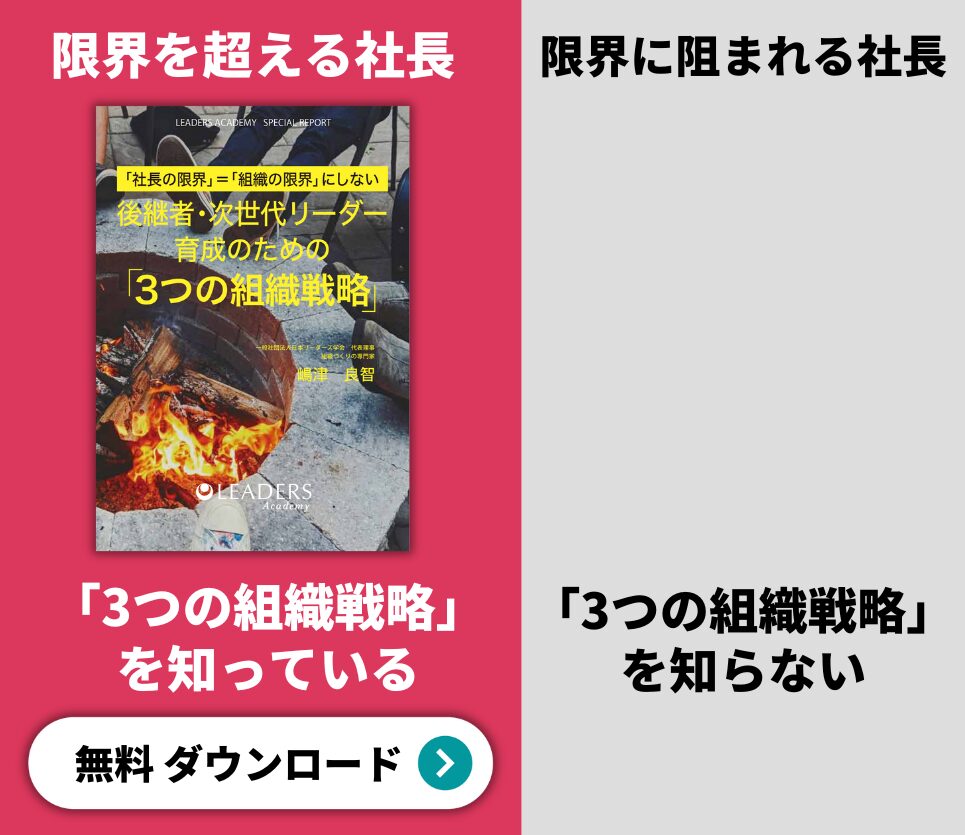
 【無料】「組織づくりの秘訣」
【無料】「組織づくりの秘訣」