「組織が動かない」「新しい取り組みが進まない」といった問題に直面していませんか。硬直化した組織は変化への対応力が低くなり、競争力を失う原因になります。そのため、次のような悩みを持つ方も多いでしょう。
- 組織の硬直化とは何か、詳しく知りたい
- 組織の硬直化が問題視される理由やデメリットを知りたい
- 組織の硬直化が起こる原因とその解決策を知りたい
組織硬直化の原因はさまざまで、原因にあわせた解消方法を実施することが重要です。また、具体的な事例やデジタルツールなどを把握しておくことで、組織改革をスムーズに進められるでしょう。
本記事では、そもそも組織の硬直化とは何か、問題視される理由や根本的な原因はどこにあるのかなどを解説し、解決策や具体的な取り組み事例についても紹介します。
組織の硬直化とは?どのような意味?

組織の硬直化とは、意思決定や業務の進行が停滞し、変化に対応できなくなることを意味します。「組織の形骸化」「組織の機能不全」なども同様の意味で使われることが多いです。
企業が成長して規模が大きくなると、組織は複雑化しがちです。部門間の連携不足や、古いルールに縛られることで、組織全体が柔軟性を失い、組織の硬直化を招きます。
例えば、トップダウンの指示が多いような組織や、ルール・規制が厳しい企業では、現場が自由に動けなくなり、新たな挑戦や変化がしにくい環境になります。
組織の硬直化を解消するためには、このような仕組みを見直し、柔軟に改革していくことが求められるでしょう。
組織づくりに対して悩みがある方は、こちらの記事を参考にしてください。
» 組織づくりとは?企業を成長させる「強い組織」の作り方 | リーダーズアカデミー
組織の硬直化はなぜ問題視されるのか

組織が硬直化すると、成長や変化が停滞し、組織全体が動きづらくなります。市場競争が激しい現代では、柔軟な対応力やスピーディーな意思決定が求められる機会も多いため、非常に重要な問題となるでしょう。
組織の硬直化が問題視される具体的な理由としては、以下などが挙げられます。
- 新たな挑戦の機会を逃す
- 社員のモチベーションが低下する
- 市場競争力が低下する
ここでは、上記のような、組織硬直化がもたらすリスクについて詳しく解説します。
新たな挑戦の機会を逃す
硬直化した組織では、新しい取り組みや挑戦が阻まれます。例えば、企業が縦割り組織となることで承認プロセスが複雑になり、現場からのアイデアがタイムリーに実行に移せなくなるでしょう。
市場の変化が激しい現代では、スピード感を持った意思決定が重要視されます。一方で、硬直化が進んだ組織では「今までのやり方」が重視され、新しい発想が敬遠されがちです。その結果、他社が新しいビジネスチャンスを掴む中で自社は変化に遅れ、新たな挑戦の機会を逃すことになります。
社員のモチベーションが低下する
意見が通りづらい硬直化した組織では、社員のやる気が削がれる問題もあります。特に若手社員や有能な人材は、自分の意見や提案が受け入れられないと感じると「何をしても変わらない」と諦め、モチベーションが低下しがちです。
この状況が続くと、優秀な人材が他社へ流出してしまい、離職率が高まる可能性があります。逆に組織改革を望まない人材のみが残り、より硬直化を加速させてしまうリスクもあるでしょう。社員の成長意欲や積極性が低下することで、組織全体の生産性や活力も失われ、悪循環が生まれやすくなります。
市場競争力が低下する
市場の変化に対応できない組織は、競争力を失います。新しい顧客ニーズや技術に素早く対応できなければ、競合企業に後れを取ることになるでしょう。
例えば、革新的な製品やサービスをタイミング良く市場に提供できなければ、顧客の関心が他社に移り、ビジネスチャンスを失うリスクが高まります。
組織の硬直化が進むほど意思決定が遅れてしまうため、結果として企業の成長や存続に大きな影響を及ぼすことになります。
組織の硬直化の根本的な原因

組織の硬直化は一夜にして起こるものではありません。主に以下のような原因が積み重なることで、組織の硬直化を引き起こしています。
- 縦割りの組織
- 統率者のリーダーシップ不足
- ルールや規制による拘束
- 役職者がポジションに固執
上記のような要因が重なることで社員の主体性が失われ、変化への対応が遅れるようになります。このような原因について、詳しく解説します。
原因その1:縦割りの組織
縦割りの組織では、各部門が独立して目標を追うため、組織全体の連携が不足しがちです。例えば、営業側と技術側が互いに責任を押し付け合い、対立が生じるなどのケースがあります。営業側が目先の契約ばかりを追ってしまうことで、現場トラブルを技術側に丸投げし、組織としての一体感がなくなることが多いです。
また、部門間の情報共有が不足し、組織全体の最適化や効率化を図れないことも多いでしょう。一方の部門では効率化を図れるようなアイデアが生まれたとしても、実際は他の部門で弊害が生じ、組織全体としては意味のない施策となっている可能性もあります。
このような縦割りの構造が硬直化を引き起こし、組織全体の停滞を招く原因となることが多いです。
原因その2:統率者のリーダーシップ不足
統率者のリーダーシップ不足も、組織の硬直化を引き起こす原因です。リーダーシップ不足は、各部門や組織全体の方向性を曖昧にしてしまい、意思決定のスピードも遅くなります。
経営者や管理職が明確なビジョンを示さず、意思決定を先延ばしにしていると、現場は混乱するでしょう。社員は「何をすれば良いのか」が分からなくなるため、組織全体としての動きも鈍くなります。
原因その3:ルールや規則による拘束
組織におけるルールや規則は必要ですが、過剰に厳格化されると、現場の柔軟性が失われることが多いです。「大企業病」としてよく取り上げられる問題でもあり、ルールを重視した結果、組織がスムーズに動けなくなります。
例えば、承認プロセスが複雑化しすぎてすぐに意思決定ができないと、社員は「動きたくても動けない」と感じてしまいます。この状態は組織の停滞を招くだけではなく、社員の主体性やモチベーションの低下にもつながってしまうでしょう。
ルールや規則による拘束感が強まると、変化や挑戦を恐れる組織風土が生まれてしまいます。
原因その4:役職者がポジションに固執
年功序列の仕組みや、固定化された役職構造も、組織硬直化の原因となるでしょう。役職者が特定のポジションに居座り、部下に対して昇進のチャンスが与えられないこともあります。
役職者が自分のポジションを譲らず、若手の成長を妨げることで、新しい発想やイノベーションが生まれにくくなります。結果、組織全体としても新しい動きがなくなり、時代の変化や市場競争に後れをとる形になるでしょう。
また、役職を持たない社員のモチベーションを低下させる大きな原因にもなります。昇進を望むような人材は組織に残りづらくなり、昇進を望まない人材ばかりが残ることで、組織の硬直化を加速させる結果となるでしょう。
組織の硬直化を防ぐ解決策

組織の硬直化を防ぐためには、以下のような解決策に力を入れることが大切です。
- 横断的なコミュニケーションを促進する
- リーダーシップスキルの強化と育成をする
- 柔軟なルール運用をする
- ヒエラルキー上の肩書きを作らない
ここでは、各解決策について詳細を解説し、実践的なアプローチについてお伝えします。
解決策その1:横断的なコミュニケーションを促進する
縦割りの組織が硬直化の原因となっている場合は、横断的なコミュニケーションを促進すると良いです。部門間の壁を取り払い、横断的なコミュニケーションを促すことで組織の硬直化を防ぎます。
例えば、異なる部門間の調整ができる適切なリーダーを抜擢したり、組織全体としてのKGI(重要目標達成指標)やKPI(重要業績評価指標)を共有したりすることで、部門間の連携が深まるでしょう。
さらに、情報共有のためのオンラインツールを活用し、互いに進捗状況やスケジュールをリアルタイム共有することで、意思決定のスピードも向上します。
また、横断的な組織づくりには、「大規模で複雑なプロジェクトに対応できる」「各部門の専門知識を共有して効率的に問題解決が可能」といったメリットもあります。導入ステップや成功するためのポイント、注意点などは以下の記事で解説していますので、参考にしてみてください。
» 横断的組織とは?求められるリーダーシップや現場で活かせる組織改革のポイントを紹介 | リーダーズアカデミー
解決策その2:リーダーシップスキルの強化と育成をする
硬直化を解消するためには、経営者や管理職がリーダーシップを発揮し、組織を方向付けることが不可欠です。具体的には、リーダーシップ研修や若手リーダー育成プログラムを導入することで、組織全体の意思決定力や統率力を高められます。
リーダーが現場の意見を積極的に取り入れ、ビジョンを明確に示すことで、社員からの信頼が高まり、組織の硬直化を防ぐ効果が期待できるでしょう。
リーダーの役割ややるべきことについては、以下の記事などで解説していますので、参考にしてみてください。
» リーダーズアカデミー|10年後も成功し続ける社長の「人と組織の育て方」
解決策その3:柔軟なルール運用をする
必要なルールと不要なルールを定期的に精査し、都度見直すことも重要となるでしょう。組織にルールや規則が多すぎると、現場が動きづらくなります。
また、マニュアルが古く、長年変更されていない場合は、マニュアルを更新することも重要です。昔からのやり方や古いマニュアルは組織を硬直化させ、社員の考える力を失う原因にもなるためです。新しいアイデアが生まれた際には、マニュアルをどのように更新できるか見直し、変化を柔軟かつ積極的に受け入れる姿勢が大切となるでしょう。
現場の声を取り入れながら、柔軟にルールやマニュアルを整備することで、社員が自主的に行動しやすい環境を整えやすくなります。
解決策その4:ヒエラルキー上の肩書きを作らない
フラットな組織構造を取り入れ、肩書きにとらわれない環境を作ることで、柔軟性が高められるでしょう。ヒエラルキー上の役職や肩書きを強調しすぎると、役職者がポジションに固執し、組織の新陳代謝が起こらなくなります。
例えば、肩書きを「プロジェクトリーダー」や「ファシリテーター」といった柔軟な名称に変更し、プロジェクト単位で責任を与えることで、肩書きや年齢、役職などへのこだわりが薄くなります。
また、新規プロジェクトのリーダーを若手に任せ、上司がサポートに徹する形を取ることで、経験の浅い社員でもリーダーシップを発揮しやすくなります。
若手社員にも責任が求められる仕事を積極的に任せるようにすれば世代交代が促進され、新しいアイデア・発想が組織に浸透しやすくなるでしょう。
組織の硬直化解消に役立つデジタルツール

デジタルツールの導入は、組織の硬直化を解消する強力な手段です。特に、次のようなツールを積極的に導入することで、柔軟かつスピーディーな組織運営が可能になります。
- コミュニケーションを円滑にするツール
- 業務プロセスを可視化・効率化するツール
- データ共有・分析を効率化するツール
ここでは、目的別に役立つ具体的なデジタルツールを紹介します。
コミュニケーションを円滑にするツール
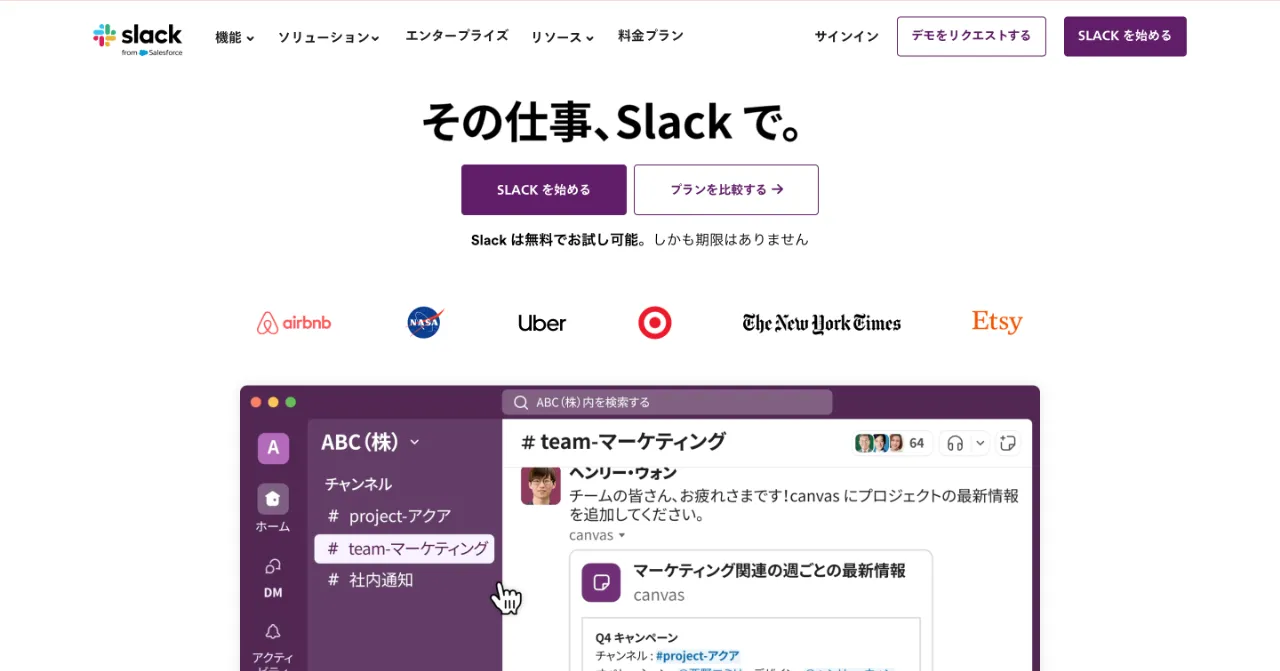
コミュニケーションツールは、部門間や役職の垣根を越えて、リアルタイムで情報共有するために役立ちます。
具体的には、次のようなコミュニケーションツールが挙げられます。
- Slack
- Chatwork
- Microsoft Teams
- Zoom
- Google Meet など
このようなツールを導入し、オンライン上のチャットやビデオミーティングを活用することで、部門間のコミュニケーションがスムーズになります。やり取りに時間がかかる無駄なメールの工数を削減可能で、会議のために営業所や部門を行き来する必要もありません。
縦割りではない横断型の組織づくりが可能となり、組織の硬直化を防ぎやすくなるでしょう。
組織間で情報共有を行う重要性やメリットについては、以下の記事で解説しています。
» 情報共有はなぜ必要?組織における情報共有で生まれる様々なメリットとは | リーダーズアカデミー
業務プロセスを可視化・効率化するツール

タスク管理やプロジェクト進行などの業務プロセスを可視化・効率化することで、組織全体が同じ目標意識で仕事に取り組みやすくなります。
具体的には、次のツールなどが役立つでしょう。
- Asana
- Trello
- Monday.com など
このようなツールは、業務の進捗やタスクの担当者を明確にし、責任の所在も明らかにします。例えば、冗長な会議や遠回りなメールのやり取りが減るため業務効率が大幅に向上し、組織の動きがスムーズになるでしょう。
また、管理職は各プロジェクトがどこまで進んでいるのか確認しやすくなり、進捗に応じてスケジュールやタスクを柔軟に変更することが可能です。進捗報告不足による遅れや認識齟齬を防げることもあり、組織の硬直化解消につながるでしょう。
データ共有・分析を効率化するツール

データ共有や分析を効率化することで、各部門が同じデータを見て動きやすくなります。組織間の認識齟齬も生じにくくなり、組織としてスムーズに動きやすくなるでしょう。
具体的なおすすめツールとして、以下などがあります。
- Google Workspace
- Microsoft SharePoint
- Tableau
- Power BI など
このようなツールを活用し、クラウド上でデータを一元管理することで、各社員が必要な情報にすぐアクセスできる環境となります。
例えば、Google Workspace内で使用できるドキュメントやスプレッドシートは、WordやExcelとの互換性もあり、オンライン上での共有が簡単です。ファイルURLを知る全員が閲覧可能な設定や、一部の社員や取引先のみが閲覧できる設定もあり、メールでいちいちファイルを添付する必要がありません。
また、BIツール(Business Intelligence)であるTableauやPower BIを導入すれば、誰でも直感的にデータ分析が簡単になり、意思決定のスピードも向上するでしょう。マウス操作だけで簡単にレポート作成ができるため、「レポート作成や分析に時間がかかる」「レポートが報告して欲しい内容と違った」といったケースを減らせます。
業務を効率化できるのはもちろん、組織全体としてスムーズな意思決定が可能となり、硬直化の解消につながるでしょう。
組織硬直化を防ぐための取り組み事例
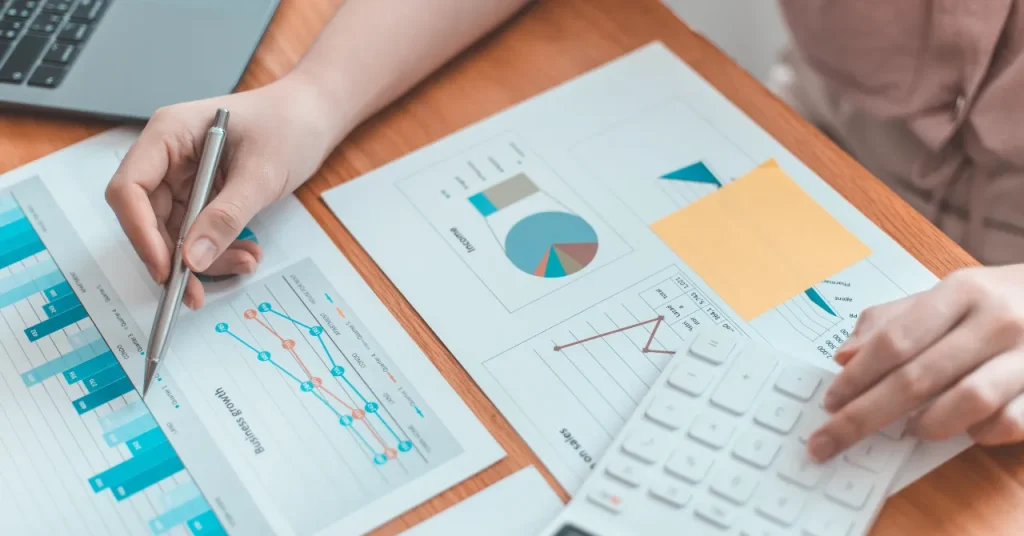
ここまで、組織硬直化の原因や、そのデメリット、解決策などについてお伝えしました。しかし、いざ解消に向けて何か取り組みを始めようとしても、実際には何から始めたら良いか分からなくなるケースも多いです。
以下では、組織改革の取り組み事例を紹介し、具体的にどのような取り組みを行うべきなのかを解説します。
上司と部下による1on1ミーティング
サイバーエージェント株式会社では、上司と部下による1on1ミーティングを月に1回の頻度で実施し、社員の不満や改善案を吸い上げる仕組みを作ることで、組織全体の効率化を図りました。
上司は部下の意見や新しいアイデアを取り入れやすくなり、部下は上司から適切なサポートを受けやすくなります。上司と部下の信頼関係構築にもつながり、組織内のコミュニケーションが円滑になりました。
このように組織の風通しを良くしておくと、現場の悩みや課題が早期に解決され、社員のモチベーション低下や、上下関係による対立も防げるでしょう。
役員とのランチタイム
株式会社アカツキでは、「役員ランチ」という仕組みを新たに作り、月に1回の頻度で役員と社員が一緒にランチできる機会を設けました。社員は特定の役員を指名してランチに誘うことが可能で、ランチにかかる費用は会社負担です。
このような場を設けることで、普段は関わりの少ない役員と社員が、信頼関係を築きやすくなります。また、社員は役員の目線でプロジェクトを捉えやすくなり、役員は現場の不満や課題を引き出せるでしょう。
役員と社員が一緒にランチをする取り組みは、階層間のコミュニケーションを円滑にし、社員のモチベーション向上にもつながります。
若手を中心としたリバースメンタリング
海外の企業であるゼネラル・エレクトリック社では、年齢を問わずに多様性を持つ取り組みとして、「リバースメンタリング」という制度を取り入れました。
リバースメンタリングは、若手社員が上司や役員に対して、新しい技術やトレンドを教える仕組みです。通常のメンター制度は上司や役員が部下を指導するものでしたが、リバースメンタリング制度ではその立場が逆転します。
具体的には、社長以下の役員に20~30代のメンターがつき、月に1回ほどスマートフォンなどのデジタル技術やSNSの活用法、若者の視点から見える消費者傾向等について助言しました。
上層部と若手の意見交換が活発化し、上層部は新しい取り組みやデジタル技術について、柔軟な視点を持つことが可能になります。
日本では、P&Gや資生堂などがこの手法を取り入れています。
硬直化は組織全体を巻き込んで解決しよう

組織の硬直化を解消するためには、経営層から現場社員まで組織全体が協力して取り組むことが重要です。
具体的には、以下のポイントを意識しましょう。
- 横断的なコミュニケーションが取れる組織づくり
- リーダーシップスキルの強化や育成
- 柔軟なルール運用
- ヒエラルキー上の肩書きを作らない
組織全体として柔軟にコミュニケーションを取れる環境や、新しいアイデア・挑戦を取り入れやすい環境を整えることが、特に重要です。
本記事で紹介した原因や解決策、取り組み事例を参考に、まずは自社に合った方法から実践してみてください。柔軟で活発な組織運営を目指し、変化に強い企業づくりを進めていきましょう。
企業を成長させるための「組織の作り方」については、リーダーズアカデミー特製の「組織づくり」お役立ち資料をお届けしています。お気軽にお申し込みください。
» リーダーズアカデミー|10年後も成功し続ける社長の「人と組織の育て方」
【監修】
黒田 訓英
株式会社 ビジネスバンク 取締役
早稲田大学 商学部 講師
中小企業診断士
早稲田大学商学部の講師として「ビジネス・アイデア・デザイン」「起業の技術」「実践起業インターンREAL」の授業にて教鞭を執っている。社長の学校「プレジデントアカデミー」の講師・コンサルタントとして、毎週配信の経営のヒント動画に登壇。新サービス開発にも従事。経営体験型ボードゲーム研修「マネジメントゲーム」で戦略会計・財務基礎を伝えるマネジメント・カレッジ講師でもある。
日本証券アナリスト協会認定アナリスト(CMA)。日本ディープラーニング協会認定AIジェネラリスト・AIエンジニア資格保有者。経済産業大臣登録 中小企業診断士。






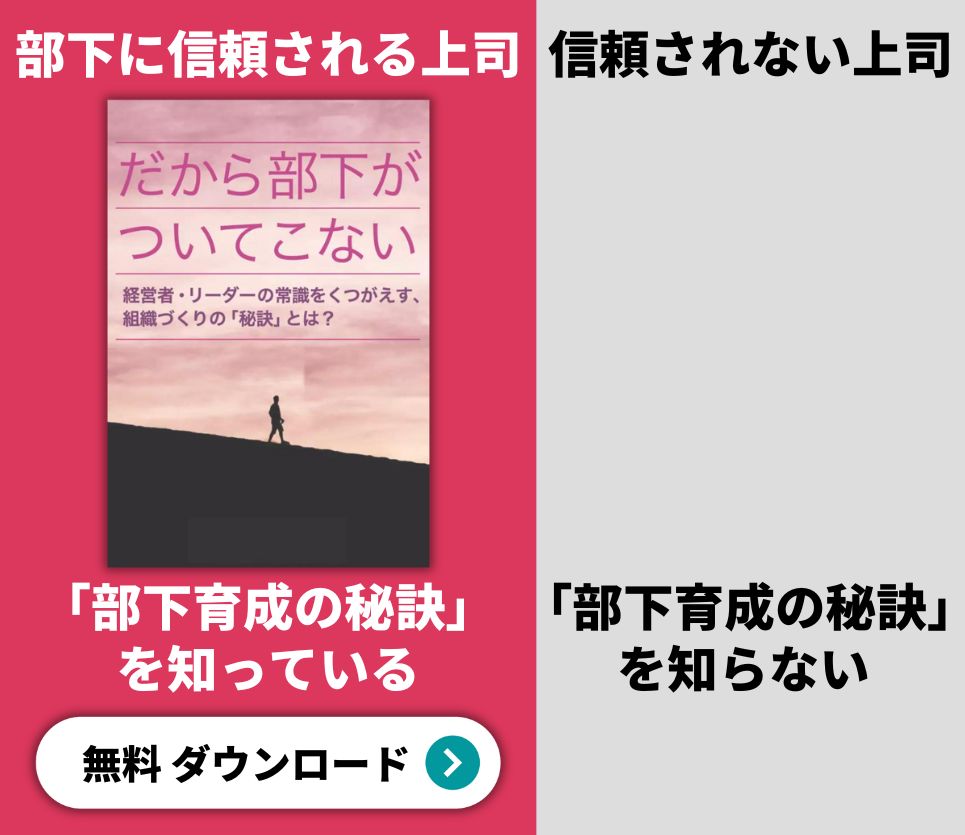
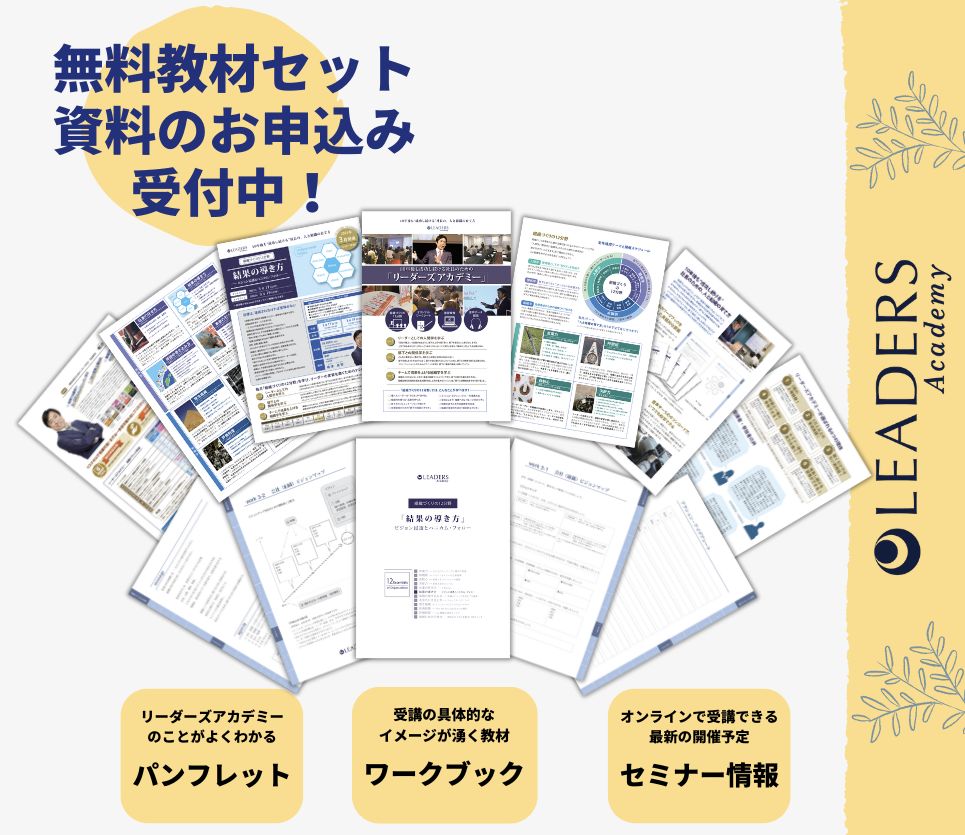
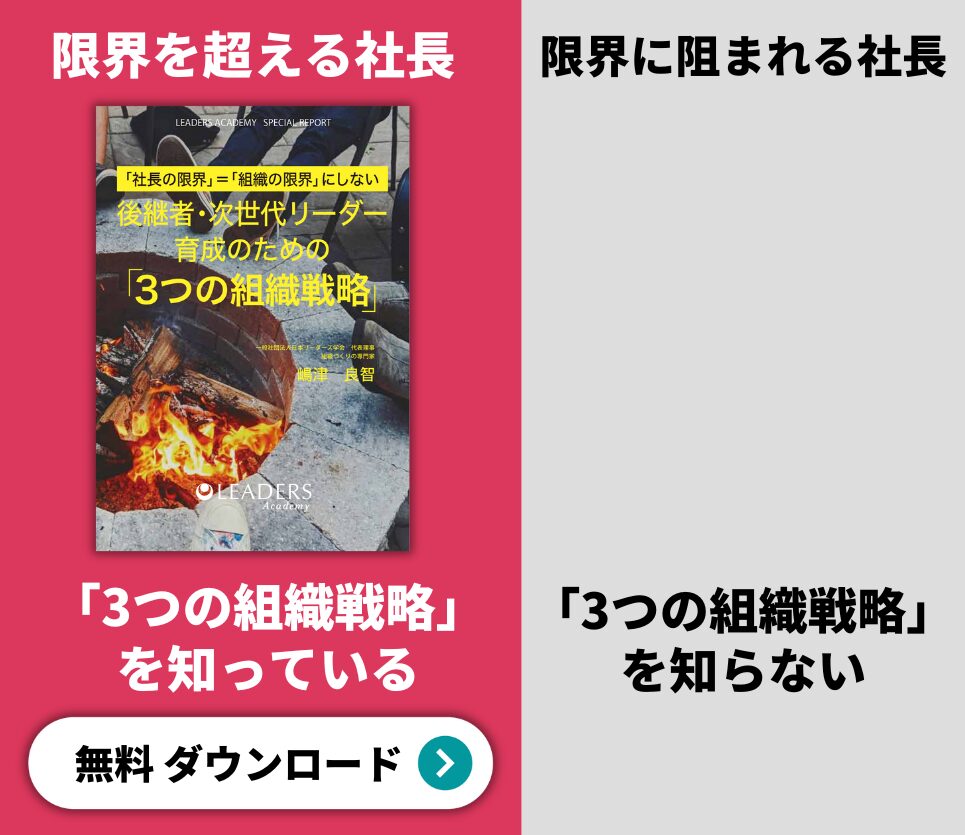
 【無料】「組織づくりの秘訣」
【無料】「組織づくりの秘訣」